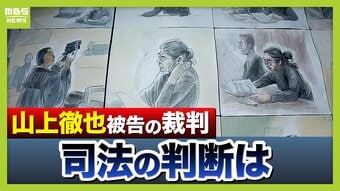浅野:まさに今 言った話だと思うんですけど、ある時に、「モンゴル」って映画を撮っていた時だと思うのですが、パッケージの話じゃないんですね。映画館で流すから映画… ってわけではない。 というのは砂漠のような街で、小さいインターネットカフェがあって、そこで子どもたちが集まって、一つの画面にかぶりついてダウンロードした映画を見ていたんですね。
この子たちが、こうやって「喜びを持って映画を見てる」ってことが一番重要だし、なんか…ここに届かないんだったら、映画じゃないな…と思ったんですね。
その時に、何か自分の中で「余計なタガ」が外れて… 作品が大きいからとか、小さいからとかじゃなくて、僕が「何かできそうだ」とか、「やってみたい」とかっていうことがあれば、そこには何か共通した「映画的な要素」は生み出せるんじゃないか…っていうのはありますけどね。
Q:今 タイパ(タイムパフォーマンス)だとか ドラマ等を「早送り」で観る人もいる時代ですが、作品の視聴動向に対する、自身の想いを伺ってもよろしいでしょうか?
浅野:なぜ「早送り」するかっていうと、まさにそうやって決められたルーティンの中で映画を作っているからだと思うんです。僕も2倍速で子どもたちが映画を見ているって聞いた時に、「だよね!」って、2倍速で映画を見ましたし・・・
なぜなら、僕を釘付けにする「何か」が、そこにはなくて、ただただ「内容を確認したいだけ」ってなっちゃっているわけですよね。でも、こっちがやっぱり心がけるべきは、「気づいたら見ちゃった」ってものを作らなきゃいけないから、そういう意味では「現場」で笑いが生まれていなければ、やっぱり「倍速」で見ちゃうと思うんですよ。
でもそれって、「現代的で面白いな」と思うし、だったら最初から倍速の映画を作っちゃえば良いし、もしくは、こうやって短編とかで どんどん映画を流すべきだと思うんで、(長編映画は)約2時間… っていうルールはね、なんか本当に 誰かが勝手に、いつの間にか作っちゃったものだから、それは本当にいらないな…と思いますけどね。

Q:「男と鳥」を観て、「浅野さんは、普段どんなことを考えているんだろう?」って小栗監督から絶賛されていましたが、どういうふうに社会とかを見ていますか?
浅野:いやもう…本当に天邪鬼ですから、ものすごくひねくれて、日々いろんなものを見て、やっぱり「当たり前であること」っていうものが、ありがたいことは いっぱいあるんですけど、やっぱりこれって考えたら「昔からずっと動いていないんだな」って事が、やっぱり溢れているんですよね。
「これって何で、こうあるんだろう?」って なんか当たり前だけど、もっと良くできるんじゃないかとか、それは、「この役をどうしたら面白くできるだろう」って考えている延長線だと思うんですよね。
普段、台本をもらって読むと、どっか頭の中にこびりついた「誰かがやったような演技」で読んでいる自分がいたりするんですね。そうすると大体、つまらないんですよ。
でも、「あ!いけない」と… こうじゃない場合ってなんだろう? ってもう1回読み直すと「こういう人だったら面白いな」 とかって…
失礼な話ですけど、主人公に僕が興味のない俳優さんがキャスティングされて、その方が台本を読んでいると、「やっぱ、つまらないなぁ~」ってなるんですけど、もし渥美清さんが…寅さんがキャスティングされてたらって想像すると、めちゃくちゃ大体面白いんですよ。
これって、やっぱり「俳優の役作りの話」だから、そっか…「つまらない役ってないんだな」って、そこで思えるわけですよ…