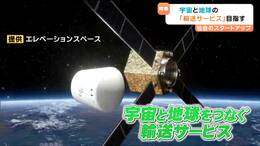明日が見えなかった日々
一方で、新たな道を開くことができた人がいる。少数民族カチンの女性ルルさん(仮名)を訪ねた。
「前よりはいいです。少し、少し、進み始めています」
2年半前に会った時は、まだ3回目の難民申請の結論が出ず、「緊急避難措置」は適用されていなかった。「仮放免」中で、働けない、健康保険もない状態で、当時の取材メモに残る言葉に「希望」はない。
「いつ捕まるか、明日のことはわからない。前は、何になりたい、何がほしいという気持ちがあった。でも長い間何もできなかった。それを考えることが苦しい。人間じゃないみたい。(40代の)この年になって、みんなに迷惑をかけていて、本当は私がいろいろしてあげないといけないのに」
父は軍事政権と戦う武装組織カチン独立軍(KIA)の将校だった。ルルさんら4人のきょうだいは祖母に育てられ、軍の迫害を恐れながら住む場所を転々とした。ルルさんも学校を7回変わらざるをえなかった。日本での難民申請では、こうした事情を訴えたが、認められていなかった。
コロナ禍の21年9月、「私は死んでいたかもしれない」ところまで追い込まれた。
新型コロナワクチンの注射を受けた後、高熱が続いた。PCR検査で陽性反応が出た。たまたまその時、先の渡辺弁護士と打ち合わせが控えていたことから「コロナになっちゃったので行けません」と連絡した。深刻な病状に気づいた渡辺弁護士が救急車を呼んだ。それで入院ができた。夜中になって肺の状態はさらに悪化し、酸素吸入にまで至った。
「息ができない、すごく苦しかった。もし1人で家にいたら、どうしていいかわからなかった」
渡辺弁護士によると、それでも保険証がないルルさんは「救急車にはお金がかかりませんか」と心配していたという。