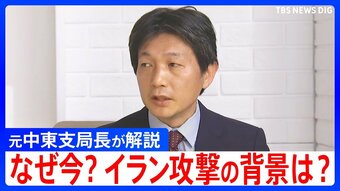ハラスメントガイドブックが出来た経緯

「舞台芸術におけるハラスメント防止ガイドブック」を作成したプロジェクトチームのリーダー・坂本ももさん
「少しずつSNSの発達の中で、昔はその場にいる人しかわからなかったようなクローズドだったものが告発されるようになってきて、それは昔はハラスメントとは言わなかった、問題視されていなかった部分があるので。なかなか改善に声を上げられないというのが業界としても続いていた中で、さすがにやっぱりもう時代が変わっていて、舞台芸術業界だけ特別というわけにはいかないというのにようやく気付いたというような」
業界を巡っては、コロナ禍での感染防止対策や国際的なMe Too運動…なども経て社団法人として様々な共通の課題に取り組んでいく流れで、今取り組むべきはハラスメントだと考え始めたそうです。
「舞台芸術におけるハラスメント防止ガイドブック」にはハラスメントになり得る事例がたくさん挙げられているので、まずはいくつかご紹介します。
「人格否定や暴言を吐く」「暴力を振るう」「キャスティングと引き換えに無理やり性行為をする」…(これはハラスメント以前に犯罪ですが!)
「拒否や抵抗に対し、役を下ろしたりギャラを下げるなど不利益を与える」「指示をする際に語気が強くなる」…など。
一方、こうした事例に対し、ガイドブックには興行主催者が取るべき防止のアクションがまとめられています。
例えば、暴言、暴力に対しては「個人の意識だけでは改善されない場合があるため、主催者は興行単位でハラスメント防止研修などを導入し、意識改革から取り組む必要がある。加害者が自身の攻撃性やストレスに向き合い、メンタルヘルスを整えることも重要で、カウンセリングやアンガーマネジメントなども有効」と載っています。
ハラスメント防止のためには、第一に主催者が「ハラスメントをしない/させない」という姿勢を示し、関係者に対して意識を共有することが何よりも大事だと指摘します。
舞台芸術は様々な形態で興行が行われていて、興行主であるプロデューサーよりも、あるセクションのプランナーの方が年上で意見しづらかったりするなど、より複雑な構造が存在します。
こうしたことから、座組ごとに実態に即したルールをガイドラインとして示し、関係者全体にハラスメントの知識を授け、防止対策を周知することが大切だということです。