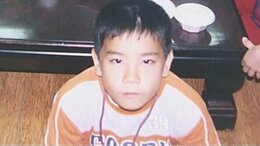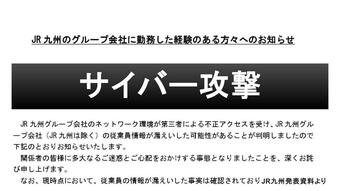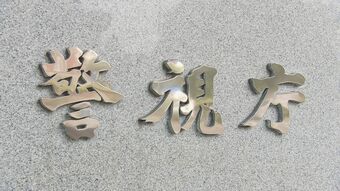“教師の自腹”問題の処方箋は…
こんな現状に対して、出来ることを考えなければなりません。
予算の問題はありますが、まずはできるところから「学校財務マネジメント」を行っていくべきと主張するのは、福嶋さんと一緒に、「隠れ教育費」の問題提起を行い、今回の調査にも参加している、公立中学校の事務職員、柳澤靖明(やなぎさわ やすあき)さんです。
公立中学校の事務職員 柳澤靖明さん
「いまお金がこれくらいあります。このお金を執行するために、こういう時に要求を事務室に出して下さいね。それで予算書を事務所が作りますよ。年度途中だとしても予備費を執行したりということもできますからちゃんと窓口として事務室を頼って下さいっていうことを共有する。で、あと自腹を切らないっていう。1人が良いから自腹切っても良いって問題じゃなくって、全体の問題なんだからというベース、土台を作っていくという研修も、やはり必要だというふうに思っています」
教職員と学校財務の担当者である事務職員が協力し合って、例えば「学校財務委員会」を設置して予算執行計画を考えていくなど、各学校が自律的な財務を行えるように、文部科学省などが、きちんとしたガイドラインを作る必要性があると思われます。
一方で、現状に於いては、すべての自腹に対して目くじらを立てるべきではないとも、柳澤さんは言います。
公立中学校の事務職員 柳澤靖明さん
「なくならなくても良い自腹っていうのが、教育に直結しないとか、運動会で緑組の教員担当だから緑に全身しようみたいなものとか、あとは卒業式の袴、一緒に着ようね~とか。そういうところはなくならなくてもいいのかなって」
教師の自腹は「なくせる自腹」「なくすことが難しい自腹」「なくならなくてもよい自腹」の3つに分類でき、まずは「なくせる自腹」を切らないようにすることだと、柳澤さんは提案します。
この問題に興味のある方は、「隠れ教育費」研究室のホームページや「教師の自腹」の書籍を、ご覧ください。
TBSラジオ「人権TODAY」担当:松崎まこと(放送作家/映画活動家)