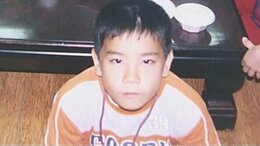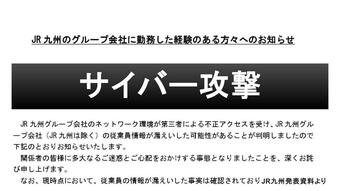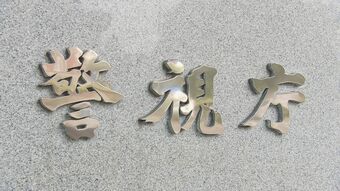“自腹”が“自腹”を呼ぶ実態
先にも挙げましたが、授業の教材から部活動関係まで、自腹は多岐に渡ります。
自治体の財政的な問題で現場で使えるお金が少なかったり、予算を使うための手続きが煩雑だったりするため、ちょっとした金額だったら、仕方ないと考えて自腹を切っているケースが少なくないと思われます。
またより良い教育を子どもたちにしようと、自腹で教材を用意したりといったケースも見られます。そうした気持ちはわかるような感じもしますが、問題は、自腹が自腹を呼ぶことです。
千葉工業大学准教授 福嶋尚子さん
「自腹を切っている主体の先生方の受け止めの分け方として、『積極的自腹』と『消極的自腹』と『強迫的自腹』という3つのカテゴリーに分けられるというふうに、分析をしています」
「積極的自腹」というのは、先に挙げたように半ば自主的に行う自腹なわけですが、こういった教師の方が居ると、同調圧力が生まれて、例えば隣のクラスの担任も、同じように自腹を切らなければならなくなったりします。
これが「消極的自腹」です。
この「消極的自腹」のケースがもっと強まって、その教師が全然納得がいってないのに、自腹を切らざるを得ない状態に追いやられるのが、「強迫的自腹」となるわけです。
今回の調査で、福島さんが大きな衝撃を受けた自腹が、「各家庭の徴収金未納の立替え」です。例えば図工での工作や家庭科の調理実習などで使うものを、保護者が用意しなかったり、費用を払わないままだったりした場合、教師の側が、それを負担してしまうことがままあるというわけです。
また部活関係でも、こうしたケースが見られるようです。
多岐に渡る“自腹”ではありますが、教師の方々が特に不満に思っている“自腹”について、福嶋さんに伺いました。
千葉工業大学准教授 福嶋尚子さん
「修学旅行など学校行事の際に自己負担が生じていることについて、不満を持たれる方はかなりいらっしゃるかなーという風に思います。例えばですけど、先生方自身も子どもたちと一緒にお昼ご飯をたべたりするわけなんですけど、この昼食代っていうのが、先生方の自己負担になっているかどうか、これも実は自治体によってかなり仕組みが異なって…」
修学旅行の場合、下見なども必要なわけですが、それに関する費用は、交通費をはじめ全てが自腹なんてケースもあるようです。有給ではない日曜日に下見に行かされて、その上自腹だったりなど、先生方も大変です。