強度行動障害 必要な支援とは
山本恵里伽キャスター:
高齢の親が障害のある子どもを見る『老障介護』という言葉がありました。ご本人にとっても、親御さんにとっても、本当に深刻な問題だと痛感しました。
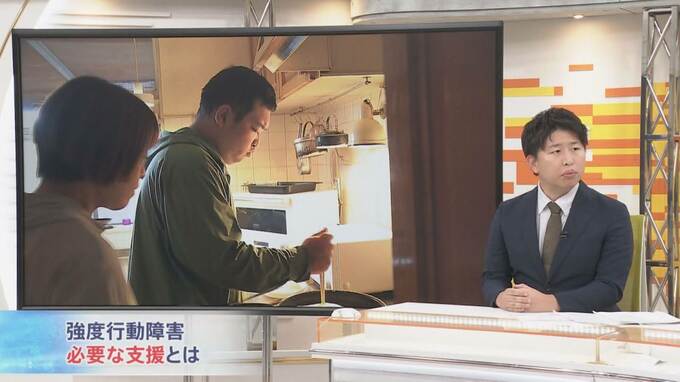
MBS 萩原大佑 記者:
強度行動障害は、自分や他人を傷つけたり、物を壊したりするなど、本人や周囲の暮らしに影響を及ぼす行動がしばしば起こる、特別に配慮した支援が必要な状態のことをいいます。
生まれつきの障害ではなく、周囲の環境や関わりによって現れる状態です。亮太さんも、普段の生活では、穏やかにご両親と暮らしています。ただ亮太さんの場合、日々の生活のリズムが変わるとパニックを起こします。このとき両親も大変なのですが、実は亮太さん本人の方が、強い不安や緊張に襲われているのです。それを上手く周囲に言葉で伝えられず、行動という形で出てしまいます。
強度行動障害の人が幸せに生活できるよう、私たちも障害に関する理解を深めて、安心できる環境づくりが必要だと思います。
村瀬健介キャスター:
社会としては、どのような受け入れ体制をつくることが求められていると考えますか。
萩原 記者:
障害者が暮らす場所については、施設や病院から地域に移す『地域移行』が世界的な潮流であり、国連もその考え方を推し進めています。最も大事なのは、障害者本人がどこで誰と生活するかを選択する機会を持てるようにすることです。
しかし、強度行動障害に関しては、特にグループホームなど地域への移行も簡単には進まない現実があります。国は、強度行動障害のある人を支援できる施設を整備し、何よりも支援する人材の育成をバックアップしていく必要があると考えます。
そうすることで、亮太さんが幸せな暮らし方を自分で選択できる機会を得られるようになることが大事だと思います。














