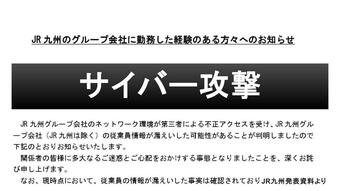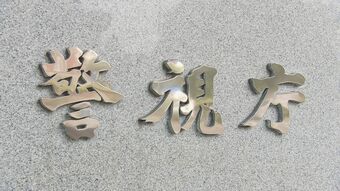ガザ地区に入る物資の量は激減 薬品不足も深刻に

パレスチナ子どものキャンペーン海外事業チーフ 中村哲也さん: (以下、中村さん)
ガザ地区では子供たちの学習機会が、この1年にわたって失われてしまったという現実があります。避難キャンプに集まっている子供たちに、紙や鉛筆を用意し、寺子屋のような勉強の場を作る活動も行っています。
荻上:
現地に物資を届けることが困難だったと聞いていますが、この点はいかがでしょうか?
中村さん:
ガザ地区に入る物資の量が激減しました。以前は1日500台のトラックがガザに入っていましたが、200台以下になり、5月以降その数が大幅に減りました。 エジプトやヨルダン経由で一部物資を入れていますが、まだまだ厳しい状況が続いています。
荻上:
また、メンタルヘルスや衛生環境の悪化も懸念されています。この点についてはいかがですか?
中村さん:
衛生環境や栄養状態の悪化が人々の健康に深刻な影響を与えています。野外クリニックを設置し、妊産婦や乳幼児への支援を行っていますが、薬品の不足が深刻です。
荻上:
現地のスタッフからはどのような状況が伝えられていますか?
中村さん:
非常に厳しい状況の中で、スタッフたちは一生懸命活動しています。しかし、300名以上の人道支援従事者が戦争の犠牲になりました。スタッフたちは身の安全を優先しながらも、支援を続けています。
ガザでは多くの病院やクリニックが機能停止していますが、負傷した子どもたちの中には、ガザの外での手術やケアを必要としている子どもたちもいるわけです。
例えば、そうした子どもたちを日本に受け入れるために、日本政府が「命のビザ」みたいなものを発給するなど、日本だからこそできる支援があればと考えています。
荻上:
鈴木さん、我々ができる支援についてはどうお考えですか?
東京大学 特任准教授 鈴木啓之さん:
直接的な支援として、現地で活動する国際NGOや国連組織への寄付が最も効果的だと思います。また、日本社会ではこの1年を通してパレスチナ問題や中東情勢への関心が高まりました。今後もこの関心を保ち、現地の人々を理解するための取り組みを続けることが必要です。
荻上:
現地で活動している方々への寄付や支援が重要だということですね。
===
<聞き手>
荻上チキ:
評論家。メディア論を中心に、政治経済、社会問題、文化現象まで幅広く論じる。NPO法人「ストップいじめ!ナビ」代表、「社会調査支援機構チキラボ」所長。著書『ウェブ炎上』『いじめを生む教室』『みらいめがね』など。
南部広美:
フリーアナウンサー。日本短波放送で株式市況、経済ニュースを担当後、J-WAVE ニュース室勤務 アナウンサーとして7年間勤務。 J-WAVE “ Jam the world”、“Tokyo コンシェルジュ”、“みうらじゅん安西肇の GOLDEN TIME”NHK BS “こだわりライフヨーロッパ”ほか、CMナレーションなど多数。