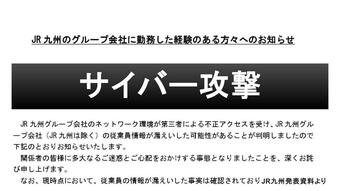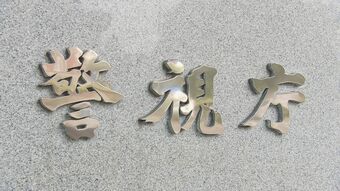荻上:
なるほど、攻撃の手段や範囲というのも拡大していますよね。例えばレバノンではヒズボラ関係者や民間人に対する攻撃も続いています。こうした手段の拡張についてどうお考えですか?
鈴木さん:
ヒズボラに対する通信機器を使った攻撃にはとても驚かされました。ヒズボラが購入して構成員に配布した通信機器に、イスラエルによって事前に爆発物が仕込まれていたとのことです。また、ヒズボラの指導者ナスララ書記長の殺害もありました。過去に例のない規模、性質の攻撃だったと思います。
荻上:
イスラエル軍は民間人を巻き込まないように限定的に攻撃していると説明していますが、この説明と実態の乖離についてはどう思われますか?
鈴木さん:
イスラエルはガザ地区でのでの戦闘でも、民間人の犠牲者を最小限にしているとの立場です。しかし、実際には民間人の犠牲者が多く出ていることを、私たちはすでに知っています。レバノンでも、やはり市民の犠牲が出ており、インフラも壊されています。このる現実を直視すべきです。
南部:
リスナーからメールが届いています。「ガザ侵攻から1年、パレスチナの命の犠牲と戦争の拡大が胸を痛めます。国連や国際司法裁判所は何のためにあるのでしょうか?」
荻上:
このメールについて鈴木さんのご意見は?
鈴木さん:
国際刑事裁判所(ICC)や国際司法裁判所(ICJ)から、この1年にいくつか重要な判断が示されています。特に今年7月には、イスラエルの占領政策は国際法に違反しているとの勧告的意見がICJから出されました。こうした司法判断に準拠して国際社会全体がこの問題に対してどれほど行動を起こせるかが課題です。
注目の記事
“空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行

立憲・公明が「新党結成」の衝撃 公明票の行方に自民閣僚経験者「気が気じゃない」【Nスタ解説】

「僕の野球人生を最後このチームで全うできればいい」楽天・前田健太投手に独占インタビュー

受験生狙う痴漢を防げ 各地でキャンペーン SNSに悪質な書き込みも 「痴漢撲滅」訴えるラッピングトレイン 防犯アプリ「デジポリス」 “缶バッジ”で抑止も

宿題ノートを目の前で破り捨てられ「何かがプツンと切れた」 日常的な暴力、暴言…父親の虐待から逃げた少年が外資系のホテリエになるまで 似た境遇の子に伝えたい「声を上げて」

「timelesz」を推すため沖縄から東京ドームへ――40代、初の推し活遠征で知った “熱狂” 参戦の味、そして “お財布事情”