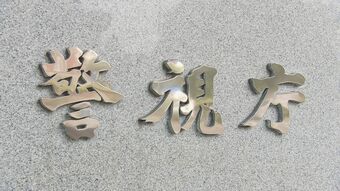ガザ紛争の開始から1年。中東情勢が混迷を深める中、戦火の行方はどうなるのか、東京大学特任准教授の鈴木啓之さんとパレスチナ子どものキャンペーン海外事業チーフの中村哲也さんと共に考えます。
(聞き手・荻上チキ、南部広美)
前例のない事態が次々と生じている
南部広美(以下、南部):
東京大学の特任准教授である鈴木さんは中東地域研究の専門家であり、パレスチナ問題を研究しています。著書には『ガザ紛争』や『パレスチナ/イスラエルの<いま>を知るための24章』などがあります。この1年間の戦闘についてどうお考えですか?
東京大学 特任准教授 鈴木啓之さん(以下、鈴木さん):
過去の事例に照らして考えると、ここまでガザ地区での戦闘が長期化するのは想定外でした。この1年、前例のない事態が次々と生じているという認識です。
荻上チキ:(以下、荻上)
今回の長期化の背景要因についてはどうお考えですか?
鈴木さん:
ネタニヤフ政権が戦闘の継続に非常に前向きであるという点が大きいと思います。人質の解放を軍事力で実現するのだという姿勢を崩していません。そして、ガザでの戦闘が続く限り、レバノンのヒズボラやイエメンのフーシ派からイスラエルを標的とした攻撃が続き、イスラエルが攻撃を実施する。戦火が拡大している状況です。
荻上:
ガザ侵攻に加え、レバノンへのへの軍事侵攻があり、イランとの戦争も懸念されますが、この点についてはいかがですか?
鈴木さん:
レバノンへの軍事侵攻について、イスラエルは「限定的」と言っています。過去の事例に照らせば数ヶ月で終わるはずなのですが、ガザ地区での戦闘がこれほど長期化していることを踏まえれば、まったく楽観視はできません。
さらに、いま懸念されているのは、最終的にイスラエルとイランとの戦争に発展するリスクです。イスラエルはガザ地区のハマス、レバノンのヒズボラ、イエメンのフーシ派といったグループの背後にイランがいると見ていますし、イランはガザ情勢やイスラエルによる攻撃を理由として、10月1日に新たにミサイル攻撃をイスラエルに対して実施しました。
いま、イスラエルからの報復攻撃がどのような形で実施されるのか、その規模次第ではイスラエルとイランの本格的な戦争に発展しかねないと危惧されています。