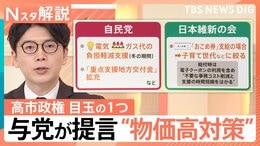台風10号による記録的な大雨で熱海市では複数の道路が通行止めとなり、一時「陸の孤島」のような状態となりました。
道路に土砂が流れ込んだことが主な原因でしたが、災害時の孤立化にはどのような対策が必要なのでしょうか。

道路に勢いよく流れる茶色く濁った水。2024年8月30日、熱海市と函南町を結ぶ県道は川のようになっていました。この3時間後…
<東部総局 竹川知佳記者>
「午後5時半すぎの熱海市、熱海梅園前の交差点です。中央に拳大の石がごろごろと転がっています。上流からは茶色く濁った水が流れ出しています」
20センチ近い大きさの石を含む土砂が流入し県道は、半日に渡って通行止めとなりました。
茶色く濁った水は土砂災害が起きる直前の危険なサインだったのです。台風10号の影響で降り続いた大雨では、県内の広い範囲で土砂崩れが相次ぎました。

静岡県熱海市では火葬場にも土砂が流れ込み、近隣の市や町に頼らざるを得ない状態が続いています。場所によっては平年の8月1か月分の3倍を超える雨量を観測した今回の大雨。
県道に土砂が流れ込んだ熱海市でも8月30日、24時間の降水量が374.5ミリと観測史上最大を記録しました。

「ここ通れないですか」
「すみません、通行止めなんで」
「これって解消の見込みは立ってないですか?」
「そうですね、まだ」
現場では懸命な土砂の撤去作業が行なわれていましたがこの時、熱海市では複数の場所で土砂崩れが起きていました。

<東部総局 竹川知佳記者>
「熱海周辺、真っ赤になってますね。この海沿いの道もダメで、ここもダメで、ここが土砂崩れで通行止めなので、沼津には帰れないですね」

沼津に帰ろうとしましたが熱海で身動きが取れなくなりました。熱海市につながる主要な道路は3つ。海沿いを走る国道135号、熱海峠を超える県道11号(バイパスを含む)、伊豆半島を縦に通る伊豆スカイラインです。
8月30日の夜は、大雨や土砂の流入ですべて通行止めとなりました。こうした大雨災害だけでなく、南海トラフなどの地震災害が起きれば孤立状態が長引くリスクがあると専門家は指摘します。
<静岡大学防災総合センター 岩田孝仁特任教授>
「山間地域ではかなり大規模に道路が損壊したところは、復旧のまでには相当長期間かかるところも当然出てくると思いますね。長期間その中に閉じ込められてしまうっていうことは、当然のリスクとして考えとく必要があると思います」
2024年1月に起きた「能登半島地震」でも道路の亀裂や陥没、土砂崩れなどが相次ぎ、集落が孤立しました。
孤立化を防ぐために道路ではどのような対策を行っていくのでしょうか。

<県道路保全課 西原宏昌課長>
「近年のゲリラ豪雨に対してはハード整備による対応には限界がある。こうした事態に対して、交通規制の実施や車両の誘導、迂回路の案内、利用者への周知、その後に応急復旧の措置に入る。こうした手順を速やかに進められるように事前の準備が重要」
個人でできる対策もあります。
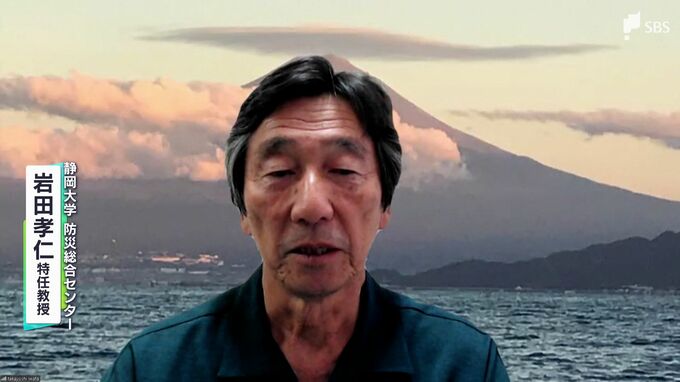
<静岡大学防災総合センター 岩田孝仁特任教授>
「例えばハザードマップをですね、あらかじめ確認をしておくとかですね。行く先々でね、やっぱり準備しておくっていうのが基本だと思いますね。事前にいろんな予報が出されているケースであれば、例えば行き先を変更するとか、中断するとか、いろんな対応ができると思います」