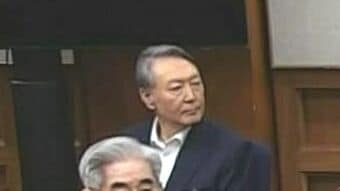■国民民主党の立ち位置 政策実現のため与野党超えて連携

ーー国民民主党のこれから立ち位置、これから目指すものというのは?
玉木:
もちろん我々も政権取りたいなと思っているし、ただ今の政治の現状を見ると、「政権交代します」と言ってもリアルさがないので、でも我々は国民のために存在しているから、その有権者国民に、我々の今の身の丈と立ち位置でどういう価値を提供できるのかっていうことを考えたときに、ひとつはこういう解説をしているってこともありますし、そうは言ってもやっぱ政策実現だと思うんですよ。政権交代というのも、政権交代が目的じゃなくて、そのことによって何か新しい政策を実現するということ。
いずれにせよ、政治家・政党は政策実現が目的であれば、今のこの人数と今の形でどうやったら政策実現できるのか、やっぱり変えなきゃいけない政策もあるし、岸田内閣がやっていることで不十分なこともあるしね。そこはやっぱり、われわれとしてどういうふうに絡んでいけば政策実現できるのかということで、実は今年の2月11日の党大会で、われわれが公約に掲げたような国民のための政策実現のためには、“政策本位で与野党を超えて連携協力する”ということを党の方針として決めているので、時には野党ともやりますけどでも、時には与党とやってですね、これもいろいろご批判をいただきましたけど、予算に賛成してトリガー条項凍結解除を求めたとか。
ちょっと旧来型じゃないかもしれませんけども、やはり政策本位で。100点満点はね小さい政党だからは無理でも、20点でも30点でも前に進めばいいなと思っているし、あと心がけているのは、やっぱり先手先手で必要な政策を提案してくことで
す。で、やったときにはなんだって言われるんですけど、これ本当に検証していただきたいんです。半年経って1年経ったらわれわれが言っていることは、必ず結構、政策テーマとして取り上げられています。例えば原発のリプレイスなんかもね、参議院選挙で、建て替えですね、原発の再稼働でリプレイスまでちゃんと公約に書いてあるのはうち(国民民主党)だけですから。自民党も書いてないです。党内では言うけど、選挙に堂々と掲げて戦ったのは国民民主党だけですからね。
■旧統一教会問題 きちんと調べてオープンにするのが第一歩

ーー旧統一教会問題が出てきて、政治と宗教の関係っていうよりも、政治家と宗教の変な関係ということが、うわーっとなって、肝心の政策が何も来てない。それを片付けないと次へ進めないですよね
玉木:
統一教会の問題は私自身も実は6年前に民進党時代に3期生だときに、寄付を2万円と1万円もらっていたということが明らかになりました。弁解するわけじゃなくて本当は知らなかったんですね。当時、勉強会で社会保障制度の講演をしたときのメンバーの1人に、講演を聞いていていただいた人の中に世界日報という関連が深いとされる新聞の元社長の方がいて、確か会費か何かでいただいたものを寄附金計上して、それで言われたんです。
ただ私は早いうちにそういうのを全部調べてオープンにして記者会見したので、その私の映像がいろんな民放も含めて、お昼の番組を使われて、「玉木さん大丈夫?」って、全国からいっぱいいただいたんですが、まずひとつは政治家がきちんと調べて、それをつまびらかに全部明らかにするということと、仮に疑惑を持たれるようなことがあれば、ちゃんと経緯も含めて説明するということが大事だと思います。
今わが党の中で議論しているのは、今回のことは政治と宗教の問題ではなくていわゆる政治とカルトの問題というか、これは別に宗教法人に限らず、悪いことをする反社会的なことをする組織団体は政治だけじゃなくて社会全体から排除しなきゃいけない。調べてわかったんですけど、例えばある宗教法人が不法不当な行為をしていることを所管庁である文科省や文化庁がタイムリーに知ることができるかというと、銀行だったら何かあったら金融庁がちょっと来いって言って質問したり報告徴求を求めたりすることが法律にも書かれている。
実は宗教法人法にも、質問報告の権限はあるんですが、旧統一教会についてはですね、1回も使われてないですね。これただ政治的な圧力が働いたというよりも、やっぱりあの戦前の国家神道のことがあったので、国家が簡単に宗教法人に、仮に質問であろうが報告であろうが、やっぱりその所管官庁から来たらちょっとやっぱり萎縮するので、それは相当な違法の疑いがあるとか、著しく公益を害するような場合とか、その疑いがあるときしか使えないようにしている。ただ疑いがあればできるので、行使したらいいんだけど、なんかね、裁判で有罪が確定しない限り質問をしないとかね、さすがにちょっと厳格に運用しすぎなのかなと思うので、その質問とか報告をして、現状を正しく把握するときの要件をもう少し、ちょっと狭めすぎているのを、ちょっと明確にした方がいいのかなという、そういうことも含めて今党内で検討しています。
ーー信教の自由な話もあるし、なかなかこれは難しいですね
玉木:
一部テレビのですね、情報番組でこれよく出る10の基準なんですが、結論から言うと、皆さんこれはフランスでも使われていません。一定の判断基準にはなるんですけれども、裁判の基準にもならなくて、つまり、フランスでも反セクト法というのがあるのはその通りなんですけど、ただやはり信教の自由という憲法上保障された自由が日本もありますから、そことの関係で、まずカルトだセクトだということを定義する定義はありません。
フランスも、それやっぱり難しいので国家が「お前はセクトだ」とか「お前はカルトだ」って、いちいち言い始めると、それは信教の自由に関わるので、フランスもいろんな議論がある中で、カルトやセクトを定義することは法律でやっていません。やっているのは何かというと、カルト的な逸脱行為というその不法な行為をしたものについて有罪を受けたら駄目だという法体系にしています。
ただ、その違法な行為を、ひとつ新しく刑法上の類型を設けて、例えば子どもであったりとか精神的にまいっているとか、そういう脆弱な状況を利用して損害を与えるような行為をしたときには罰しますという、新しい犯罪類型を作ったのは確かなんです。たださっき言ったように、あくまで規制しているのは行為であって、そういったものの脆弱性を利用するような、濫用するような行為も含めて、違法なことをやった団体は駄目ですよとしているので、やっぱカルトとかセクトとか、お前はカルトだって決めているわけじゃないので、その法体系はやはりね、慎重に構築されているし、仮に日本でも今回、何か制度改正をするのであれば、そこの憲法上の信教の自由には十分配慮したですね、あくまで規制すべきは対象者じゃなくて行為だということは、やっぱり原則として守らなきゃいけないなというのが、現時点でのわれわれの検討の考え方です。