ホロコースト経験したイスラエルと被爆地の連携
「もちろんロシア人の方は素晴らしい方いっぱいいるが今のロシアの国家の体制としては大統領を呼んだとしても、長崎のメッセージはなかなか伝わりにくい。むしろロシアの偽情報作戦(ディスインフォメーション)に利用される可能性がある。ロシアとイスラエルを区別するのであれば、ここで区切ることは可能だ」
「被爆者がいない時代が近づいている中、被爆地長崎として、今後どうやって平和のメッセージを世の中に発信していくのか?被爆者への依存度が高い被爆の実相の継承に加えて、人道を軸に、他の非人道的な扱い結末を受けた人々と横連携しながら世界に訴える普遍的なビジョンを打ち出していくことが必要 」
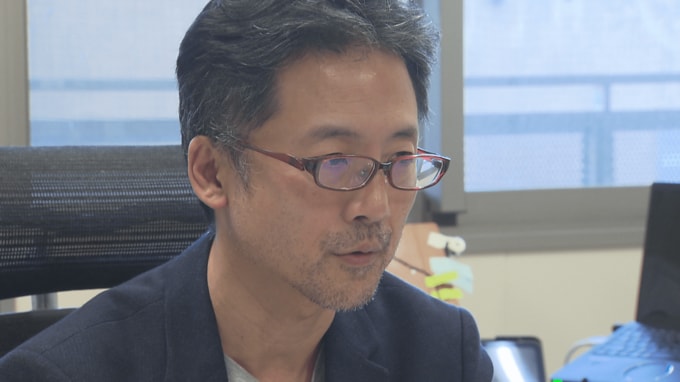
「イスラエルはホロコーストを経験した国。そういった国と広島・長崎の横が連携をしていく、その上で今やっていることはどうなのか?と発言する。そういうメッセージをきちんと発信できれば普遍的な説得力あるのではないか。今回そうした対話のきっかけとなり得た機会ではあった」

西田教授は、被爆地の判断に対する各国の反応は、いま国際社会が直面している核リスクへの危機感の高まりをあらわしている、と指摘しました。被爆地として、「警備上の理由」とは別に、非人道的行為に対しきちんと思いを世界に発信すること、非人道を極める核兵器が三度使われないための責任が改めて問われています。














