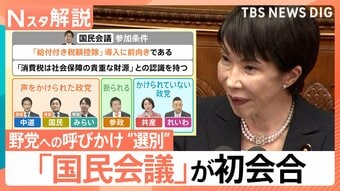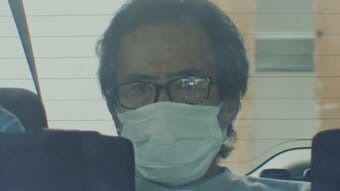助走スピードと橋岡の成長
高校3年シーズン(16年)はシーズンベストこそ7m75で、数字的には5㎝しか伸びていない。だがその記録は高校日本一を決めるインターハイという大舞台で、それも向かい風1.6mという悪条件の中で出した。
「インターハイの2週間前にポーランドで行われたU20世界陸上に出場しました(7m31で10位。2年後の同大会は7m92で優勝)。優勝したキューバの選手が向かい風(1.8m)で8m00を跳んだんです。海外で試合をしてきたことで、帰国後も向かい風とか悪条件でも跳ばないといけない意識になっていた。それも大きかったと思います」
その頃から走力も上がって、4×100mリレーでインターハイの決勝を走っていた。だが助走スピードは遅い、と大学1年頃まで言われていた。インターハイで陸連がバイメカニクスデータを測定しているが、前年のインターハイ優勝者が助走スピードが速かった。その選手と比較すると遅かったが、渡辺先生は「ゆったりした動きなので遅く見えるだけ」だと断言する。
「助走スピードより、助走のリズムをしっかり覚えることや、踏み切りへのアプローチの感覚を一番大事にしていました。それが良い踏み切りに結びつく部分ですから。でも助走スピードを抑えろと言っていたわけではありません。試合の中で自然にスピードが上がればいい、と考えていました」
良い踏み切りを絶対に崩さない。その中で助走スピードが上がって行けば、記録も伸びていく。「高校時代に8mを跳んで不思議はなかったです。高3の頃はもう、将来的には8m50は行くと思っていました」
高校卒業後、日大の森長コーチのもとで、助走スピードを上げる取り組みにも着手した。実際、大学3年の19年シーズンに当時日本新の8m32をマークしたときは、助走中の最大スピードは10.67m/秒と日本ではトップクラスになっていた。世界陸上ドーハでは8位に入賞している。20~21年は助走スピードは変わっていないが、記録の安定度は上がり、21年の東京五輪は6位に入賞。そしてメダルを目指すため、助走スピードのさらなるアップを目指して22年シーズン後にタンブルウィードTCでトレーニングを行い始めた。
しかし助走スピードの上昇は、一時的に走幅跳の記録の低迷につながった。
「助走スピードが1段階上がれば、踏み切りの難しさは2段階上がる」と、橋岡自身、今年1月に渡米する際の取材で話していた。渡辺先生も今季の橋岡を見て「今が一番苦しんでいるかもしれない」と感じている。だがその挑戦ができるのも、橋岡の踏み切り技術が絶対に崩れないからだ。渡辺先生も教え子が新しい助走を身につけて、高校時代に予想した8m50を跳ぶことを期待している。
橋岡の一番の武器は、大学時代の森長正樹コーチは「渡辺先生が教えた踏み切り」と指摘する。その渡辺先生は、橋岡が強くなった一番の理由は「1つのことをやり続けられる精神力」だと思っている。いずれにしても橋岡が積み重ねてきたことが、最終的に助走スピードのアップへのトライをする現在に至った。
橋岡がパリ五輪で日本人88年ぶりのメダルを獲得に成功すれば、それは逸材の成長局面に合わせた指導をしてきたコーチ陣の功績でもある。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)