ウキクサの大繁殖でどのような影響が?
ウキクサは枯れると腐敗して水質を悪化させるほか、水面を覆いつくしてしまうことで、水中の光や酸素の不足につながり、生態系にも影響を及ぼすことが懸念される。

そして、実務的な影響も出ている。
(都城土木事務所・鏡園義幸課長)
「船での往来っていうのができなくなっておりまして」
県では、ダムの管理のため、船に乗って地形の状況や土砂崩れがないかなどを 監視しているが、ウキクサの繁殖によってそれができなくなっているという。

(都城土木事務所・鏡園義幸課長)
「(船の代わりに)周りの道路などを利用する形で、徒歩で確認をするというような形になってますので非常に時間を要する」
こうした問題は、ほかの地域でも確認されていて、鹿児島県の鶴田ダムでは、2019年、およそ1億5000万円をかけて除去作業を行ったが、わずかに残っていたことから次の年も爆発的に繁殖したという。


では対策はあるのだろうか。
山口教授によると、こうした植物は根絶させるのではなく、人や野生生物、産業に
影響を及ぼさない程度に、低い密度でコントロールするという考え方が世界的に定着しているという。
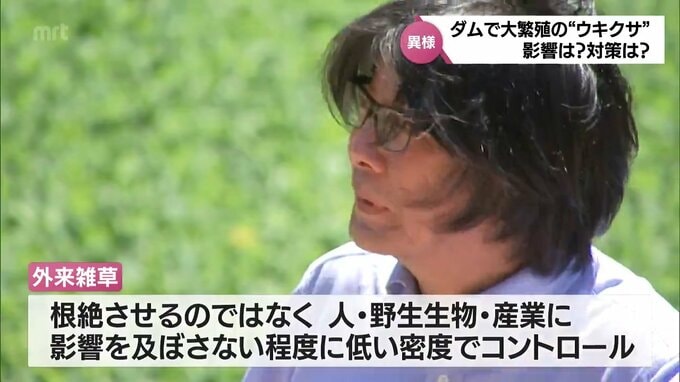
(南九州大学環境園芸学部・山口健一教授)
「雑草の場合は雑草種によって繁殖の方法がかなり大きく異なります。したがって市民の方が、いつもは見慣れない雑草が急激に増えているようというようなところを見かけられたらぜひ、市町村とか県、あるいは河川管理事務所のようなところにお知らせをしていただけると良いと思います」
県では、これまで人力でウキクサの除去を行ってきましたが、2キロ以上に及んでいるため効率的な除去方法を検討中だということです。
また、ボタンウキクサを持ち帰ったり育てたり販売することは法律で禁止されています。














