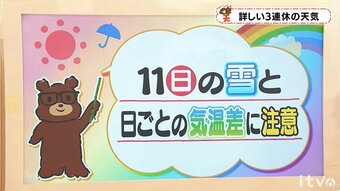伊予高校への統合が示された松山南高校砥部分校の存続を求める地元の思いを取材しました。

「75年続いてきた歴史を知らない間に2年間で決めた計画でその歴史をつぶすんですか。」(参加者からの拍手)
県教委の担当者:
「先ほども言いましたように子どもの数は着実に減っていく。学校の存続の危機というのもある。今のままの状況を続けていくのではなくてもっと広い視点で。」
砥部分校の存続を求める地元住民らに対し、県内の高校で唯一の「デザイン科」を残すための方策だと主張する教育委員会。説明会は、予定時間を超え議論は平行線をたどりました。
1948年に砥部高校として開校した松山南高校砥部分校。デザイン科のみの単科高校で、3学年あわせて120人の定員に対し現在、生徒数は107人。
校内には、陶芸を学ぶための実習室などが設けられています。
窯の中には焼きあがったばかりの生徒の作品が・・・

「夕方5時に火を入れると次の日の夕方5時に焼きあがっている。」
窯元と同じ本格的な設備があり教員によって厳重に温度が管理されていました。ここまで充実した実習設備のある高校は全国の中でも珍しいといいます。

「(生徒は)幸せ、めっちゃ楽しいと言っている。窯もそうだがろくろも多分西日本一だと思う設備では。」
窯元として活躍している卒業生から指導を受けたり、卒業前の生徒が制作展を開いたりするなど、地域と連携しながら教育が行われてきました。
現在、砥部焼の窯元のおよそ3分の1を砥部分校の卒業生が占めています。
そのうちの1人、大西先(おおにし・はじめ)さんです。砥部分校を1994年に卒業し、父親から窯元を受け継ぎました。

「砥部分校がなくなると初めて聞いた時すごい危機感を感じた。初めてこの砥部分校に入学してきて砥部焼そして陶芸に触れる生徒さんはすごく多い。そういう中から砥部焼の未来を背負って立つ陶工が生まれてきたという経緯がたくさんあるのでその活動がなくなるのはこれは砥部焼業界にとっては何もメリットがないと思った。」
分校の存続を願う一方で大西さんは、少子化による生徒数の減少を踏まえ、複雑な胸の内を明かしました。
砥部分校存続の会 大西先副代表:
「やっぱりこの世の中の流れとして統合していくというのが日本全国当たり前なのでそれも受け入れなければいけないなと思う気持ちもある。」
7月29日大西さんら卒業生と保護者、在校生らが集まり、砥部分校存続の会を立ち上げました。代表は、昨年度のPTA会長、中川礼(なかがわ・あや)さんに決まりました。
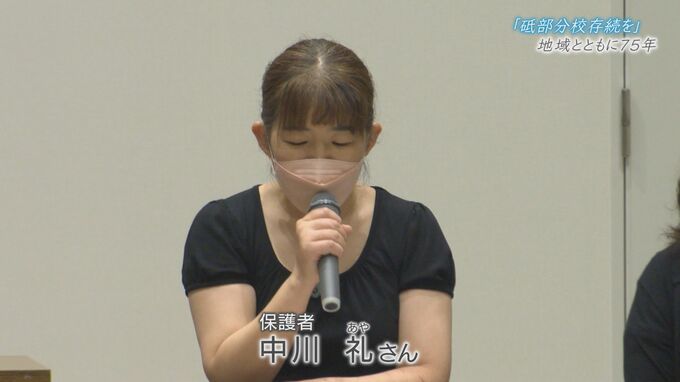
「私の子どもも砥部分校が本当に大好きでこんなに愛されている学校は他にないと思う。」
砥部分校存続の会 大西先副代表(卒業生):
「今回の愛媛県教育委員会の考え方っていうのは悔しいというのが本音。1月には結果が出てしまう。5カ月間しか私たちの活動はできない。そういった中で最善の案を僕たちで見つけて陳情していって。」
生徒会長 得井ひよりさん(在校生):
「7月のニュースを見て在校生も元々そういう話は全然聞いてなかったので急でびっくり。砥部分校にしかない設備があるのでその設備が砥部町と密接につながっていてあれがなくなるっていうのがちょっと判断が早すぎるかな。」
砥部分校存続の会の皆さん:
「署名活動始まりました。お待たせしました。」