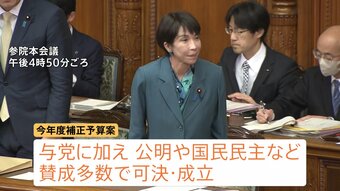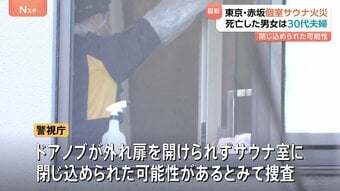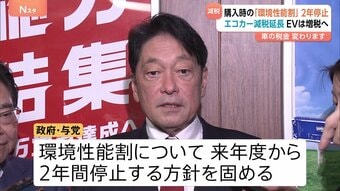中国は、負のスパイラルから抜け出せるのか!?
――金融システムの話でいうと、預金保険というようなシステムが日本にはあって、バブル崩壊のときには長銀をはじめ、大銀行が潰れたが10兆円単位のお金を出して預金の保護を図った。中国ではこういうことはなかなかできないのか。
東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:
当時の日本は、預金保険機構というのがあって本当に助かったと思うが、なお足りなければ、政府が保証すると。中国は日本に倣って、預金保険制度を2015年につくったが、できてから9年しか経っていないので、貯まったお金がわずかしかない。だから補償する能力は限りがある。結局、政府がどこまで補償するか。補償するということはお金が欲しいわけで、必要あるので、どうするかというと、結局最後は特別国債を発行してどんどんお金を刷る。やりすぎると、ハイパーインフレそれからスタグフレーションが非常に強硬に入っていく可能性が高くなると思う。
――不動産バブルが崩壊して立ち直っていく過程では市場メカニズムが働いて、例えば不動産価格が落ちるところまで落ちたら、需要が回復してくる、あるいは金融システムも傷んだものを、潰して、そして金融システムを再生させるという機能が市場メカニズムにはあるが、今の中国では、なかなか底打ちの市場メカニズムが働かないということか。
東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:
市場メカニズムが機能しない理由の一つは制度の欠陥を直していない、改革していないから。いろんな制度の欠陥と法律を見直していかなければならない。もう一つが、非常に残念なことに、我々中国という社会、中国人の国民性というのはとても資本主義的だ「競争が好きで平等が嫌い」。日本は反対で「競争が嫌いで、平等が好き」。残念ながら、中国は社会主義でこのシステムやっているから、本来ある活力を殺してしまっている。習政権前は経済が順調に成長してきたのは、自由を与えたからだ。今自由を奪われていて、統制強化されているから、ますます活力が出てこないからどんどん負のスパイラルに入っていく。
――この大不況を底打ちして新しい成長のステージに行くという道筋はなかなか見えてないか。むしろ習近平政権の優先事項はそこにはないということか。
東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:
3中総会に対する期待が強かったと思う。何らかのメッセージが出てきて、思い切って方向転換しようと期待していたが、なかったために市場が失望してしまった。これから10年どうなるのか、習近平政権が本当に舵を切るのか、このまま統制を強めていくのか、今日のこの段階でいえるのが、習近平政権の頭の中では、安全を優先的に考えて、経済の改革や市場の開放は二の次になっている。なので、なかなか楽観的な見通しは示せないと思う。(社会の安定の方が大事だということか?)社会の安定というよりも、共産党の指導体制の安全・安定を優先に考えている。
――苦境を脱するというきっかけを掴むのは、難しいのか?
東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:
いま負のスパイラルに入っていて、プラスのスパイラルに持ち直すには、やはり人民に自由を与えなければいけないのではないだろうか。
(BS-TBS『Bizスクエア』 7月27日放送より)
==================
<プロフィール>
柯 隆さん
1988年来日
富士通総研などを経て現在、東京財団政策研究所の主席研究員
中国経済の専門家