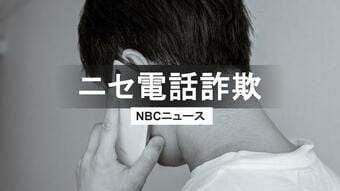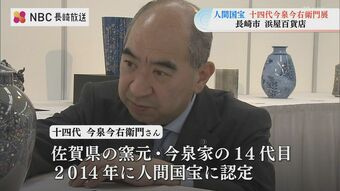大村市は現時点で「変えない」
総務省は2024年9月にも、「改めてご判断いただきたい」との文書を大村市に送付した。しかし大村市の園田市長は「現場レベルでは実務上の支障はなく、社会保障制度の確認は住民票の記載のみで判断しない」などとして「特段の修正等を行わない」との考えを示している。
園田市長は会見の中で「多様性を認める町であるために、理解を広げるために、パートナーシップ宣誓制度を導入した」と述べ、当事者の希望に沿った現場の対応は「間違っていなかった」と改めて表明。
総務省が今回の回答で再考を促す根拠の一つに、住民票は「できる限り統一的に記録が行われるべき」とした1999年の最高裁判決を提示したことに対し、「当時から国民の意識は大きく変わってる。この機会を捉え国として議論を進めていただきたい」と逆に注文を付けた。

市によると、全国の4分の1以上にあたる400以上の自治体がパートナーシップ宣誓制度を導入しており、12の自治体は同性カップルの住民票記載について大村市と同様の対応を検討または方向性を決定しているという。
「普通に暮らす」という願い
カミングアウト後、母親との音信不通が続く松浦さん。拭い去れない傷と孤独。でも、同性婚が認められても・認められなくても、自分の心が変わるわけではない。藤山さんというパートナーが隣にいる安心と喜びを力に、同じ境遇で苦しむ人たちに心を寄せる。
松浦さん:
「住民票の問題は僕たちのところに舞い降りてきたように感じる。だからできることは最善を尽くしたい。LGBTQ当事者のなかには、もっともっとしんどい思いをしている人もいる。だから僕たちから行動していきたい。同じように認めてほしい。平等であってほしい」
藤山さん:
「私たちも異性の夫婦と同じ。ただ穏やかに普通に過ごしたいだけです」

「自分らしく穏やかに暮らしたい」それは誰もが願うこと。LGBTQ
自認者への理解が進む一方、行政対応で「普通ではない」とされる扱いを受け、傷ついている当事者たちがいる。
松浦さんと藤山さんの《住民票続柄》記載問題は、書類の書き方ひとつで、悩み傷ついてきた当事者たちをさらに追い込むことも、認めることもできることを教えている。同性カップルの社会的権利について、議論が進んでいない現実も示している。議論が停滞したままでは、現実と行政対応の齟齬の中で傷つく人が続く恐れがある。自分らしい生き方を支える社会とは?2人は声を上げ続けている。