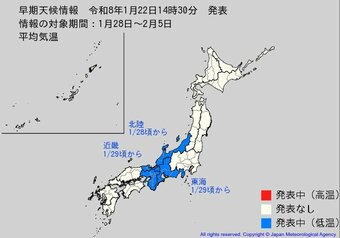絵画取引で裏金を捻出
ここで裏金「3億2,000万円」に使われた絵画と、同じ絵画が取引されていた銀座の画廊による脱税事件を振り返っておく。
この事件は1993年11月、銀座にある「フジヰ画廊」の社長が「横山大観」「ピカソ」「シャガール」などの絵画200点の売買をめぐって25億円に上る所得を隠し、法人税10億円を脱税。東京国税局査察部の告発を受け、法人税法違反の疑いで東京地検特捜部に逮捕されたというものである。
手口は複雑だった。特捜部によると「フジヰ画廊」の社長は、かねてから親しい画商と組んで、お互いにそれぞれの「絵画」の価格を、あえて仕入れ価格よりも安く設定し、損失を覚悟で取引する。つまり同じ価格で「相対取引」したように見せかける。
そうすると金額は同額なので、現金の動きはないが、「帳簿上は赤字」が生じる。そこで別の絵画取引で得た「利益」を、この「赤字」によって法人税を「減額」していたのだ。損失を装った絵画は「倉庫」に隠し、ひそかに売却していたという。
このように絵画ビジネス独特の流通ルートを悪用していたのである。
特捜部では、問題の絵画が「フジヰ画廊」から、複数の画商を経由して、野村証券と関係が深いとされた「M美術商」に渡り、「M美術商」と同社の取引によって裏金が捻出されたと判断した。
「絵画が裏金に使われる理由は、取引額が非常に高額に上るため、取引が繰り返されるごとに多額のバックリベートが生まれる。価格決定プロセスが不透明だから、裏金づくりには都合がよかった」(元検察幹部)
特捜部の調べによると、裏金づくりに使われていた絵画は、フランスの印象派の代表とも言われる画家の「ルノワール」や「モネ」、日本で高い人気を誇る女性画家「マリー・ローランサン」など10数点、取引の総額は30億円という高額に上ったとされる。
この取引によって、「M美術商」から野村証券に還流した「バックリベート」は「4億円」に上ったとされ、特捜部ではそのうちの「3億2,000万円」が、同社から総会屋・小池隆一に提供された現金にあてられたと見ていた。


東京地検特捜部が解き明かしたスキームはこうだ。
社長の酒巻が1995年の株主総会で、どうしても決議したい案件が「大タブチ」「小タブチ」と呼ばれた両田淵の取締役復帰だった。その株主総会対策および損失補てんの「非常手段」として考えたのが、小池隆一に対する「現金の提供」だった。
しかし、表のカネでは処理できない。そこで総務担当のF常務が、古くから付き合いのあった「M美術商」に「3億円」の裏金の協力を求めたのだ。
ところが「M美術商」は裏金「1億円」ならすぐに調達できるが、残り「2億円」は4月以降でないと難しいと回答。そのためF常務は、いったん系列の「野村ファイナンス」から急遽、個人名義で「2億2,000万円」の融資を受ける。これに加えて「M美術商」から調達した「1億円」とあわせ、なんとか現金「3億2,000万円」を工面し、小池の要求に間に合わせることができたのである。
そして問題の1995年3月24日、東京・日本橋にある野村証券本社応接室にジュラルミンケースが持ち込まれ、白昼堂々、現金「3億2,000万円」が総会屋に提供されたのだ。
スキームの最終処理はこうだ。F常務は後日、裏金「2億円分」を上乗せして「M美術商」から絵画を購入する仕組みで「2億円」を手に入れた。別の画商から調達した裏金「3,000万円」とあわせて「2億3,000万円」を「野村ファイナンス」への返済などにあてた。「M美術商」から最初に調達した裏金1億円は、絵画購入の際に上乗せして処理した。
F常務は絵画取引については社内では決定権を持っていたとされ、特捜部の取り調べに対し、こう供述したという。
「あくまで帳簿には、野村証券が『絵画を購入したという記録』しか残りません。社長には『カネがどう動いたのかはわかないようになっています』と説明していた」
裏で処理されたはずの裏金の存在を浮かび上がらせたのは、くしくもバブル経済の余韻が残る1993年に粂原検事が摘発した「フジヰ画廊」の事件だったのである。
絵画や彫刻など美術品取引による裏金作りは、バブル期の事件ではたびたび登場した。かつて政界へ裏金として流れたのではないかと言われた40億円の金屏風をめぐる「平和相互銀行事件」や不透明な200点の絵画購入が問題となった「イトマン事件」、三菱商事を経由した取引をめぐる「ルノワール絵画疑惑」、そしてまたしても「総会屋」小池隆一事件で絵画ビジネスの「裏金捻出のからくり」が浮かび上がったのである。(敬称略)
(つづく)
TBSテレビ情報制作局兼報道局
「THE TIME,」プロデューサー
岩花 光
◼参考文献
立石 勝規「東京国税局査察部」岩波書店、1999年
日本経済新聞「事件の裏に“名画”あり」1997年7月6日朝刊