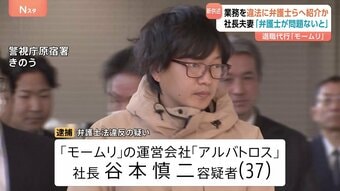3.エデュケーショナル・マルトリートメントによるトラウマ
知識や技術の獲得を強要する大人たちは、子どもが幸せになるために「強制は必要」と認識している。子どもたちを自由にすれば成績は上がらないと考え、成功する子どもを育てる「いい大人」であるためにも、あらゆる手段を使って教育しようとする。そうして、厳しい指導によって子どもが「成功」を収めた場合、それまでの厳しい指導はむしろ賞賛され、本人のトラウマは封印され、批判はタブーとなるのである。
虐待行為を愛情による教育と信じる親に育てられる被虐待児は、長期間にわたって親の教育観を刷り込まれて育ち、自らも「できること」に執着してしまう可能性がある。
幼稚園や学校でも「特定の内容ができること」を求められる中で、他者からよい評価を受け続けることで自己肯定感を保ち、周囲に認められようとする。それができない場合、良い子でいられない自分を責め、自他への信頼感や他者との愛着関係、自己効力感を持てないままに育つ。
大人の「できることがよいこと」という価値観が内在化されてしまうので、失敗や停滞は、肥大した超自我に責められる原因となる。非難を避けるためにできる限り大人の言うことを聞くようにし、仮面をかぶって優等生になってやり過ごしている場合もあれば、それができずにおどおどしたり反抗的だったりひねくれたりした態度によって、さらに他の大人たちを刺激し「何とかしよう」という気持ちをあおり、新たな虐待を誘ってしまう場合もある。
一方、そのような「正しい」価値観は、友人たちからは受け入れられ難い。できる子であれば、「優等生」「ひいきされている」として特別扱い、つまり仲間外れにされて孤独感に苛まれたり、友だちの前ではできないふり、やっていないふりをするなどして同調する努力が必要だったりするし、できない子であれば、大人に反抗的になったりいわゆる非行に走ったりして大人を嘆かせ、あきらめさせようとする。いずれにせよ、やりきれなくなったときに自傷行為に走ることがある。
被虐待児は、他児との比較や人権の学習によって自分が悪いわけではないと気づくまでに、トラウマによって傷つき、複雑な心性を身につけてしまっていることが多い。守ってくれる他者がいない少人数家族や学級の中では抵抗は成功しない。そもそも大人に「教育的」とみなされたこと以外についてはネグレクトされ、子どもたちが日常生活の中で徐々に身をつける能力や常識を獲得できていない場合もある。
多様な価値観の下で生活する子どもや、多様な場で様々な人に出会い、さまざまな生き方を見る機会のある子どもは、主たる養育者の影響を受けつつも、他者からの新しい情報によって、その価値観を上書きして自分の価値観を作っていくことができる。しかし、新しい情報もまた同じ価値観であれば、それは固定観念として不動の価値観になっていくだろう。
エデュケーショナル・マルトリートメントは、このように幼少期から長期にわたって家庭や学校の文化の中で体験され続ける。それは養育者や教育者の組み合わせによって、さまざまなパターンで子どもたちに影響を与える。加害者は一人ではない。むしろ多数が関与している。
親や教師はしばしば、自分のイメージする姿や世の中に受け入れられる姿に子どもを育て上げるのが役割だと信じている。また、子どもに対し上から「良いと思うこと」をして「あげる」ことが大切と考えている。そもそも子どもの言葉を聞いていたらわがままに育つ可能性があるから阻止しなければならないと考えている人は多い。子どもと民主的な対話をするという文化が残念ながら日本にはない。子どもは自分の所有物であり統制すべき対象であると思い込んでいることさえある。
大人の中にも、日本の一般的な子育ての価値観はおかしいと感覚的に思っている人がいる。しかし、同調圧力のある社会において、皆がそれを良しとしている「文化」の中で、別のあり方を選択することは難しい。ましてや自分の子どもが社会の中で安全かつ協調的に育つことを望むから、自分の子どもを他の子どもたちと違うように育てるのはリスキーで、避けたいことなのである。