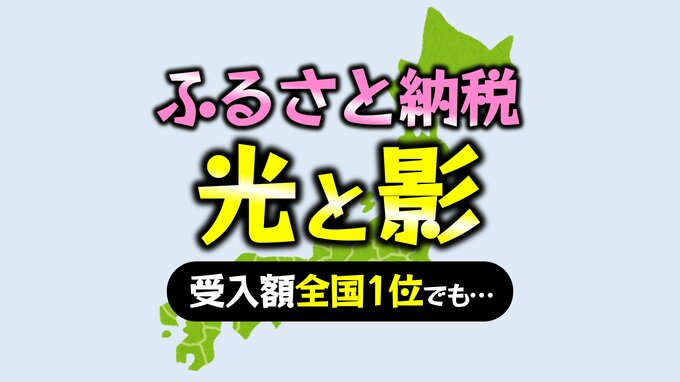総務省は、ふるさと納税のルールについて、2025年10月から、寄附額に応じてポイント等を付与する「ふるさと納税仲介サイト」を通じて寄附を募集することを禁止すると発表した。
総務省の松本総務大臣は、現状のポイント付与による競争は過熱と指摘したうえで、返礼品や寄付額に応じたポイント目的ではなく、あくまで寄附金の使いみちや目的に着目して「ふるさと納税」してほしい、と述べた。
ただ、大手通販サイト・楽天市場などを運営する楽天グループでは、この方針に反対の意を示していて、楽天市場のトップページ等で『「ふるさと納税へのポイント付与禁止」に反対するネット署名へのお願い』を通じて、署名活動を行っている。
また、楽天グループ株式会社の代表取締役会長兼社長の三木谷氏のX(旧Twitter)によると『ポイントは「弊社負担」でお手伝いさせていただいております』とのことで、ポイントの原資が寄附金に含まれているとする総務省の方針とは異なる見解を示している。
そもそも『ふるさと納税』って?実施者はわずか2割未満…
そもそも「ふるさと納税」とは、自分の選んだ自治体に寄附(=ふるさと納税)した場合に、その寄附額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度だ。
例えば、東京都在住、30歳独身の男性正社員であれば、平均年収約500万円(※1)。総務省のふるさと納税目安額によると、独身で年収500万円の場合のふるさと納税の目安の上限額は約61000円(※2)。
※1 30歳男性の平均年収は『女性が結婚相手に求める年収は? 男性の平均年収570万円でも、30歳男性の現実は…【都道府県別 平均年収ランキング】』より。
※2 ふるさと納税の目安の上限額は記事の後半に掲載しています。
この場合、3万円のふるさと納税を行うと、2000円を超える部分の2万8000円(=30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除される。
この控除される所得税と住民税は、それぞれ控除のタイミングが異なり、
▼所得税 ふるさと納税した年の所得税から控除
▼住民税 ふるさと納税した翌年の住民税から控除
となっている。
しかし、この控除のされ方は複雑で、所得税の控除は税率から算出できるが、住民税については、基本分と特例分に分かれて、その年の収入がはっきりしない中で控除上限額を計算するのは至難の技だ。
制度の複雑さや手続きの煩雑さなどもあって、ふるさと納税を行った人の割合は、納税者約6000万人に対して、2023年度の控除適用者数は約900万人と、2割に満たない数字になっている。