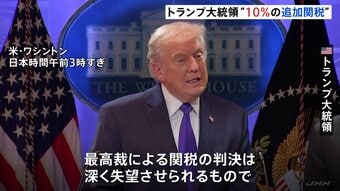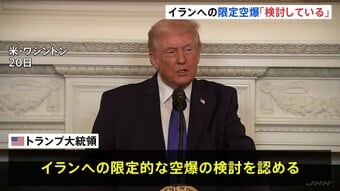二宮和也主演で6年ぶりに日曜劇場に帰還する『ブラックペアン シーズン2』。シーズン1に引き続き、医学監修を務めるのは山岸俊介氏だ。前作で好評を博したのが、ドラマにまつわる様々な疑問に答える人気コーナー「片っ端から、教えてやるよ。」。シーズン2の放送を記念し、山岸氏の解説を改めてお伝えしていきたい。今回はシーズン1で放送された1話の医学的解説についてお届けする。
※登場人物の表記やストーリーの概略、医療背景についてはシーズン1当時のものです。
佐伯式の凄さ
大人の心臓の手術は大きく分けて3種類あります。
1. 冠動脈バイパス術と言って心臓の周りにある血管(1~2mm)に迂回路(バイパス)を作る手術。
2. 弁膜症手術:心臓の中にある扉(弁)を修理(形成)するか取り替える(置換する)手術。
3. 大動脈手術:瘤になった大動脈や壁が割れてしまった(解離した)大動脈を人工血管に置き換える手術。
<佐伯式とは>
佐伯式とは弁(心臓の中の扉)を修理する手術です。ただ扉の修理と言っても心臓の中はたくさんの血液に満たされていますので、そのまま心臓を切って中の扉を修理することは不可能です。人工心肺という心臓と肺の代わりになる機械を使い、さらに心筋保護液(心臓を止め、かつ心臓を保護してくれる液)を冠動脈に注入して心臓を止めて手術をするのが一般的です。佐伯式は人工心肺を使う(オンポンプ;on pump)ものの、心臓を止めずに心臓が動いたまま(オンビート;on beat)僧帽弁を修理する手術です。
普通の扉を修理すると考えてください。人がわんさか通り、開いたり閉じたりしている扉をそのまま修理するのは難しいですよね。普通は人が通らないようにして、修理に取り掛かるはずです。
佐伯式は扉を人がわんさか通る中、扉が動いている中、修理してしまうようなものです。心臓の弁や、心臓の筋肉は非常にデリケートですので、動いている状態で修復する(針糸で縫合したりする)のは非常に難しいです。少しでも針先が狂えば組織が裂けていき、取り返しがつかないことになります。それを天才佐伯教授は100分の1mmのくるいもなく完遂してしまう。まさに神業です。
佐伯式のメリットは主に2点あると思います。
心臓を止める(心筋保護液で安全に止める)ことにより、心臓の筋肉は多少の障害を負いますが、佐伯式は心臓を止めませんので、心臓の筋肉の障害を押さえられる可能性があります。また心臓を動かしたまま修復を行いますので、弁の中を血液が通過する状態で、つまり実際の弁の動きを見ながら修復できます。扉を修理して、その後たくさんの人に実際通ってもらったら、また壊れてしまったということがないということです。