書店は守るべき?「国の支援は必要か」街の声は――

70代男性
「公的援助というのは一番良いんじゃないですか。地方の書店というのは放っておいたらどんどんなくなっていきますよね」
10代女性
「(書店を)増やしてもどんどん使う人が減ってしまうと、逆にもったいなくなるので。今の状況をそのままにしてもいいかな」
20代女性
「書店には(税金を)充てる必要はないんじゃないかな」

20代女性
「子育てとかそっちの方が、必要としている人が多いんじゃないかな」
小川キャスター:
「他にも支援が必要な中で、なぜ書店を支援するのか」という声もありました。
今村翔吾さん:
僕自身は「ごもっともだな」と思う部分もあります。それぞれの業界の中で「なんでうちを助けてくれないんだ」という意見は絶対出てくると思います。
しかし、僕自身は街の声にもあった「子育て」や「教育」という基礎的な部分は、本が担っている部分が大きいです。単純にご飯を食べていくだけではなく、教育という面も考えたら書店が必要だ、という言い訳はさせていただきたいです。
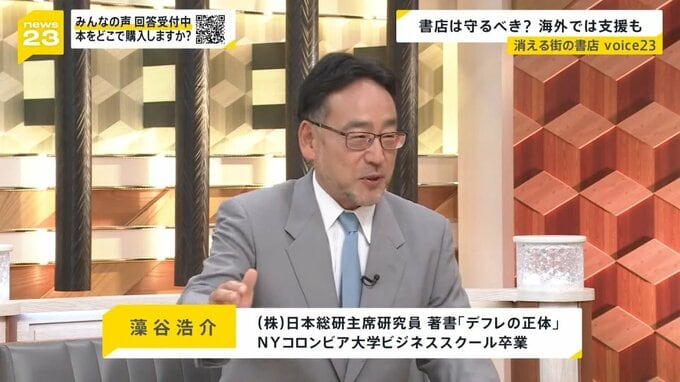
藻谷浩介さん:
まさにライブハウスや舞台芸術、美術館に行く人も一部で、行かない人に「美術館いりますか」と聞いても「いや、いらないよね」となります。
そうではなくて、「総合的にいろんなことがある」ということがとても重要。子育て支援が大事だというのはわかりますが、20年前から子育て支援をずっと言ってきた私から言わせていただくと、20年前は「そんなものは個人がやるべきで、自然に任せればいい」と言っている人がほとんどで、「税金を投じるべきだ」と言う人はごく一部でした。
書店もあと10年20年経てば、やっぱり「これは人間の非常に古い時代からあったもので、必要なんじゃないか」と。そのときには「図書館だけではなく、お金を払って本を買う人も必要だよね」というふうに戻ってくるのではないかと感じます。
藤森キャスター:
公的資金や補助金は必要だと思いますか。
藻谷浩介さん:
何をいれるかにもよりますが、今村さんのお話を伺っていると、本屋のボトルネックは家賃ですよね。人通りがあるところにあれば成り立ちますが、人通りがあるところの家賃が払えない、ということがボトルネック。
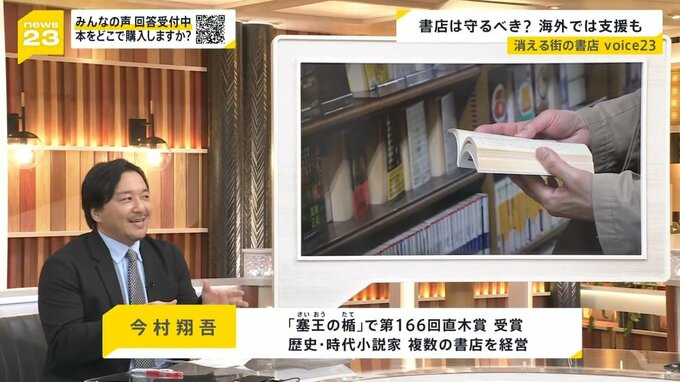
今村翔吾さん:
生活動線上にあれば入るだけの魅力はまだ持っていますが、生活動線上に利益構造的に入れないので、先ほどもあったように「わざわざ行かない」。不思議な業界でもあるんです。
藻谷浩介さん:
そういうことだとすると、保育所に似ているんですよ。例えば、駅に保育所があったら絶対便利なのに保育園は儲からないから、駅から遠いところにある。でも、JRさんが「駅に保育所を作りましょう」と一部公的支援を入れた瞬間に、みんなが非常にハッピーになる。
つまり、地代が払えないというレベルで人が来ないわけじゃない、ということであれば、その地代を安くするようなことを、公的あるいは土地を持っている民間企業は協力して、まだまだ打開できる道がある。「自然に任せてなくなったらいい」というような市場経済を完全に信じるようなことは僕にはできません。
藤森キャスター:
書店側の皆さんも「このままではいけない」といろんな努力をしていました。














