報酬もらわず卵子を提供するドナー 副作用のリスクもある中でなぜドナーに?
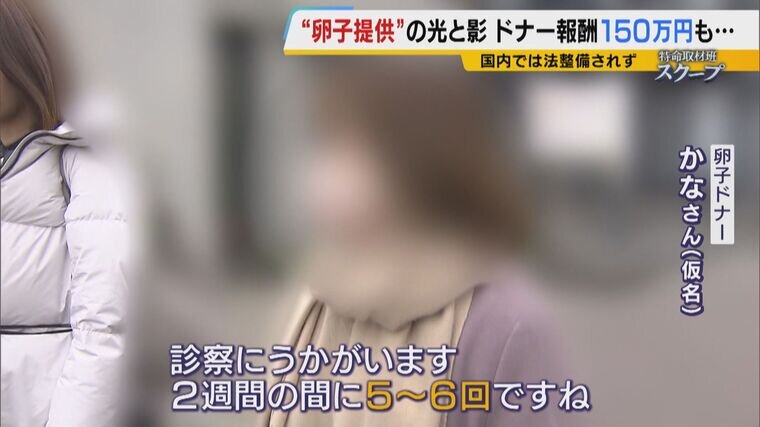
東京都内で会社員として働くかなさん(仮名)。去年12月、報酬はもらわず卵子を提供するドナー(休業補償20万円)となった。
(卵子ドナー かなさん)「診察にうかがいます。2週間の間に5~6回ですね。仕事は休みを取っていたり、シフトを調整したりするんですけど」
診察は、2週間のうちに5回ほどある。かなさんは取材した日、2回目の採卵に向け卵子の大きさなどを確認していた。
(看護師)「卵胞の方が右が0.9cmまで6個、左が1cmまでが6個になっております。いま体調とかでおなかが苦しくなったりとかはないですか?」
(かなさん)「特に問題ないです」
ドナーにかかる負担は通院だけではない。

(かなさん)「注射は毎日、決まった時間に。採卵手術の2日前ぐらいまでは打ち続けます」
2週間毎日、卵子を多く育てるために自分で注射を打たなければならない。その上、採卵手術の際の出血やお腹に水がたまるなど、副作用のリスクもある。それでもなぜドナーとなったのか、尋ねた。
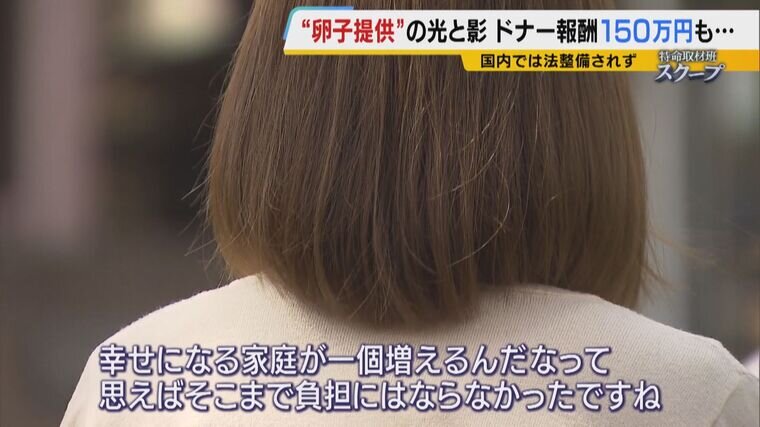
(かなさん)「自分の子どもが欲しい気持ちが強くないっていうのが大きくて、であれば望んでいるところに自分の卵子を届けられればいいなというのがあったので。幸せになる家庭が一個増えるんだなと思えば、そこまで負担にはならなかったですね」
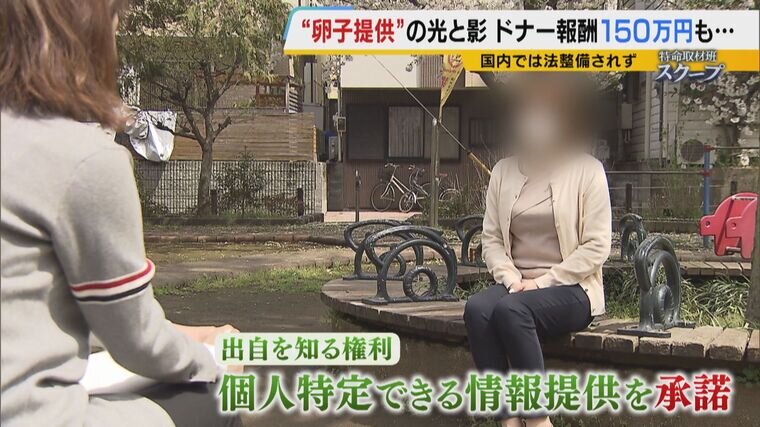
かなさんは出自を知る権利として、個人を特定できる情報を提供することを承諾している。
(かなさん)「子どもが自分の出生を知る時もくると思うので、その時はご両親と話し合っていただいて、本人が知りたければ、知れるような状態がベストだと思います。その方の人生にも関わってくるので」














