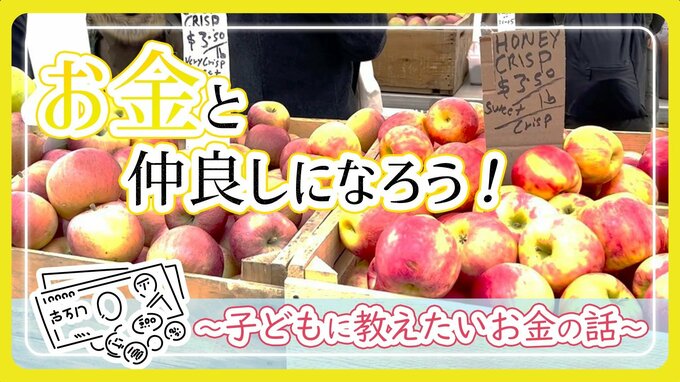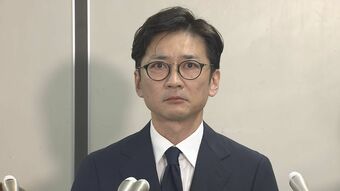急激な円安が続いています。一方で、日本銀行は金融緩和策を続け、銀行にお金を預けていてもほとんどお金は増えません。政府は「貯蓄から投資へ」を推し進めています。そんな背景などから、2022年4月から高校の家庭科の授業で資産形成の授業が本格的に始まるなど、子どもに「お金」について教える動きが加速しています。これまで日本ではタブー視されがちだったお金の話。一体どのように子どもにお金の話をしたらいいのでしょうか?
■NYの子育てで受けた衝撃 家賃の話までする アメリカ家庭の金融教育とは・・・

金融教育が浸透しているアメリカのNYで、日本の子どもたちの金融リテラシーを向上させようと活動をする女性がいます。以前、TBSの金融情報番組「ビジネスクリック」でNYの市況を伝えていた吉川淳子さんです。吉川さん自身も小学生のお子さんがいて、NYでの子育てを通して、アメリカの家庭のお金の教育に触れたことが子どもに「お金の話」をすべきだと考えるようになったきっかけだといいます。
吉川淳子さん:
アメリカの家庭では、例えば、子どもにアパートの家賃はいくらだよとか、買い物に行った時、前はお肉がいくらだったけれども、今はいくらに値上がりしたよね、何でかな?などと問いかけて、子どもたちにお金のことを考えさせる家庭が多いです。子どもたちが、お金がどのように巡るかを考え、上手に買い物をする、貯める、寄付する、などお金への意識をしっかり身に付けています。
日米の金融教育を比較した、こんなデータがあります。2019年の金融広報中央委員会の調査では、日本では学校で金融教育を受けた人の割合は7%。金融知識に自信のある人は12%でした。一方、アメリカでは、学校で金融教育を受けた人の割合は21%、金融知識に自信がある人は76%にも上りました。学校だけでなく、家庭などでお金の話を積極的にしていることが推察されるデータです。その背景には、アメリカならではの事情も見え隠れします。

吉川さん:
アメリカは何と言っても“消費大国”。お金を使うのが大好きで、借金も自分の財産と思ってしまうような感覚の人たちです。しっかりお金の管理をしないと大変なことになるので、お金のことを教えようという家庭が多いのだと思います。