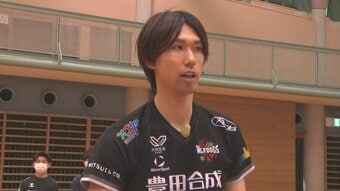アイスクリームやプリンなど洋菓子の香りづけなどに使われるスパイスの一つである「バニラビーンズ」。
黒く細かい粒が放つ “甘くて幸せな香り”はスイーツの仕上がりを大きく左右する。
マダガスカルなど主に熱帯地域で作られ、日本での栽培例はごくわずか。栽培・加工に膨大な手間がかかり、近年は“銀”より高値で取り引きされているという。
そんなバニラビーンズ、長崎県の男性が栽培・加工に挑戦し国産の希少な香りを生み出している。一般市場にはまだ流通していないにも関わらず、いまでは名だたるホテルやレストランから“指名”が入っているという。
企業の思いや開発秘話を深掘りする企画『DIG Business』。今回はノウハウも少ないなか研究を重ね、独自ブランド「ヤマトバニラビーンズ」を商品化した清水大和さんを取材した。
“香りを放つ”までには膨大な手間が…

垂れ下がっているのは、長さ20センチほどの「さや」。中に小さな種があり、これが“バニラビーンズの黒い粒”となる。しかし、この時点では香りがしない。

バニラビーンズが香りを放つには、乾燥などの工程が必要で、“とてつもない手間”がかかるのだという。
5年前からバニラビーンズを栽培している清水大和さん、36歳。
清水家は、代々農業を営んでいて、主に、祖父が始めた『ぶどう』と、父が始めた『胡蝶蘭』を栽培している。
清水さん
「それぞれが“新しい物”を始めていく農家だったので、僕もそのDNAがあるんでしょうけど、僕も何か一つ欲しかった。今まで培ってきた父や祖父の知識も使っていきたいと思い、“中間作物”を見つけようと」
バニラビーンズは、その名前から豆の仲間かと思いきや、ラン科の植物である。
『温度や湿度管理』などは“胡蝶蘭”の栽培に近く、胡蝶蘭の苗用だった空きハウスで栽培している。『間引き作業』などは“ぶどう栽培”にも通じており、従来の農作業のノウハウも活かされている。
とはいえ、バニラビーンズならではの苦労もある。
花が咲くのは数時間 10秒刻みの受粉作業
清水さん
「勝手に実をつけるものではないんですよ、バニラって。花が咲いたとき人工的に受粉させないと実がならないんですよ。実がある分、人工交配をやっているってことです」
さやの一本一本に花があり、その一つひとつに受粉させているのだという。しかも、花が咲くのは、午前中の数時間だけ。一人で受粉作業をしているため、花が咲く春は大忙しだという。
清水さん
「午前中の数時間で、多ければ千余りの数の花を人工交配していく。一つ10秒ぐらいでやってしまわないといけないんです」
受粉後、製品になるまでに約1年半

受粉から約9か月、さやの先が黄色くなると収穫である。国際基準のAグレードは『長さ14センチ以上、太さ7ミリ以上』で、清水さんのバニラビーンズは、基準を優に超えている。
しかし、品質の良い物が収穫できても “香りをうまく出せる”かどうかは、その後の加工次第だという。
バニラビーンズの水分を抜けやすくするため、清水さんが様々に研究した『企業秘密の処理』を施したあと、高温のドームハウス内でゆっくり乾燥、発酵させていく。
清水さん
「(干し始めて)2日目ぐらいで黒くなってきます。一日にだいたい1~2時間ぐらい干して、また保温。次の日も、1~2時間ぐらい干して保温をだいたい4か月間ぐらい」

その過程で次第にバニラの香りが出てくる。水分量が35%ほどになったら日陰で2か月ほど寝かせる。
受粉から、最低でも約1年半をかけ、しっとりとしてツヤがあり、香りをまとったバニラビーンズがようやく完成する。
清水さんが作る『ヤマトバニラビーンズ』は、“清水大和”さんの名と“倭の国”にちなみ名付けられた。その希少価値から、現在、輸入物のおよそ2倍の価格で直接、取り引きされている。
3代続く“挑戦者気質” 「やってダメなときはダメでいい」
50年以上前、清水さんの祖父がぶどう栽培を始めたのは、減反政策で稲作を止めなければならなくなったため。産地形成を一から始め、今では巨峰のほか、シャインマスカット、ピオーネなど約15種類のぶどうを作っている。
そして父・正人さん(70)は、胡蝶蘭栽培を始めた。新たな蘭の品種開発などにも尽力し、今も「青い大きな蘭をつくる夢」を追いかけている。

父・正人さん
「父(=大和さんの祖父)から、チャレンジする大切さを言われてきた。代々そういう家柄。そういう考えで、どんどん変えてきた」
正人さんは、大和さんがバニラビーンズにチャレンジしていることがとても嬉しいという。
父・正人さん
「やってダメなときはダメでいいんです。チャレンジをせんとダメだと思いますけどね。何の世界も一緒じゃないですか(笑)」
輸入物では叶わない “自分好み”のバニラビーンズ

長崎県雲仙市小浜町にあるアイスソルベとお菓子の店「アール・サンク・ファミーユ」。オーナーパティシエの松尾利博さんは、ヤマトバニラビーンズの“初めての取引相手”である。
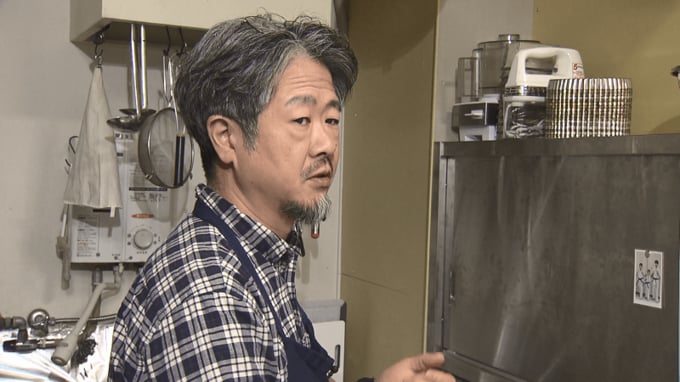
松尾さん
「(ほかの農家から)大村市でバニラビーンズ作ってる人がいますよって聞いて『え、マジ?』ってなって」
松尾さんは、すぐに清水さんのもとを訪ねた。栽培や加工の様子を見せてもらい、その手間のかかり具合などに感服。何より、清水さんの人柄に惚れ込んだ。
清水さんとの出会いによって、輸入物では絶対に叶わなかった「自分好み」のバニラビーンズが手に入るようになったのだ。
松尾さん
「長さとか、水分量とかも調節してもらったりとかして“全部選べる”んで。自分の好みのやつをいつも使わせてもらってます」
パティシエが惚れ込んだ“バニラビーンズ”
松尾さんは、清水さんの栽培や加工の苦労を知り意識も変わった。心がけているのはヤマトバニラビーンズを余すところなく使ったアイス作りである。
松尾さん
「(自分自身、ヤマトバニラビーンズに対しての)入り込み方が違うんで。思いがやっぱ違いますよね」
洋菓子店でバニラビーンズは、さやも一緒に煮出して使ったり、砂糖の中に漬け込んで『バニラシュガー』を作ったりすることが多い。そのように使った上でさやは捨てる。松尾さんも、かつてさやは捨てていた。

しかし『懸命に手間暇かけてつくっているものを無駄にはできない』と、種だけでなくさやも使い切ることにした。粉末にすると種と違ったウッディな香りがあり、また違ったバニラビーンズの魅力が楽しめるのだ。
ホワイトチョコレートに混ぜてバニラアイスにかける。清水さんとヤマトバニラビーンズに敬意を表した──その名も「ヤマトバニラ」である。

ふわっと広がる甘い優しい香り。さやの粉末が入ったチョコレート部分には、また違った香ばしさがある。
パティシエがリスペクトし、惚れ込むバニラビーンズである。松尾さんは「ヤマトバニラ」のアイスソルベを販売する時、お客さんに清水さんのことを話しているのだという。
一般市場は未流通 “使いたい”という料理人が
ヤマトバニラビーンズはまだ市場には出ていないが、SNSなどで評判が広がり、名だたるホテルやレストランなどとの取り引きが増えてきている。この日は、長崎の食材を使ったフェアを企画している東京のホテルの料理長が視察に訪れた。

羽田エクセルホテル東急 滝本雅之料理長
「魚のソースです。そこにビーンズを少し入れて混ぜると、多分、卵にバニラビーンズの香りがぷーんと…」
清水さん
「おもしろいですね」
滝本料理長
「帰ってすぐ試作したいなと思って。実はうずうずしてるんですよ」
バニラビーンズの栽培や加工についての情報は国内にほとんどなく、清水さんは「5年かけて何となく自分のやり方が見つかってきた」という。今も、SNSを通じて海外の栽培者に話を聞いたり、栽培や加工のやり方を様々なパターンで研究したりしている。開花から製品になるまで最低でも1年半。時間を無駄にしないためにも、より多くの試行錯誤が必要なのだ。

清水さん
「国産バニラビーンズって聞いて『珍しいもの』として興味を持って来られる方が多いですけど、そうじゃなくて。海外産と比べても『この香りがいい』っていう風なビーンズを研究して作っていきたいと思っています」