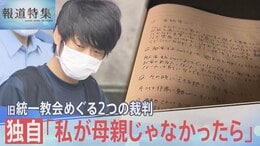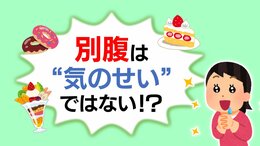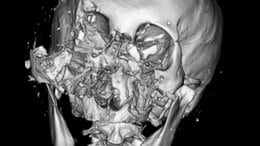インフレ低下が現実的な「期待シナリオ」
こう考えると、実質所得がプラスに転じるためには、賃金の上昇だけでなく、物価上昇率がモデレートなレベルに下がることが重要ですし、より現実的なシナリオでしょう。
昨年の3.1%どころか、日銀が目標とする2%を多少下回るぐらいまで下がって来れば、実質所得のプラスが視野に入って来ます。
その時、日銀は「何が何でも2%のインフレが必要」という立場を続けるのでしょうか。
物価上昇率が1%台でも、実質所得がプラスになって、需要が拡大するのであれば、それは望ましいシナリオなのではないのか。
日銀がマイナス金利を解除した後に2%物価目標をどう位置付けるのか、一定の柔軟化を認めるのか、極めて重要なテーマだと思います。
来年以降も賃上げを続けられるか
最も大きなハードルは、来年の春闘でも賃上げが続けられるかです。
2年連続の大幅賃上げが実現したのは、あまりに高い物価上昇に企業が応じざるを得なかったという側面が強くありました。
今後、物価上昇が次第に落ち着いてきても、実質所得がプラスになるような賃上げを続けられなければ、賃上げは一時のブームで終わってしまいます。
日本企業が「人への投資」を重視する経営を続けるのかが問われています。
そもそも、この2年、これほどの賃上げができるなら、なぜ30年間、あれほど賃金を上げなかったのでしょうか。
3年前まで「ベアゼロが当たり前」で、一転、「満額回答」の大合唱なんて、日本の経営者は結局、まわりの雰囲気次第なのか、と突っ込みたくもなります。
これだけ「変わり身」の速さを見ると、来年以降、インフレが落ち着いたとたんに「逆戻り」しないかと少し心配です。
労使、官民一体で、賃上げムードをここまで盛り上げ、凍り付いた賃金を動かしたことは大きなことです。
それを『好循環』につなげられるかどうかは、まだまだ、これからの政策や経営努力にかかっています。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)