「インフラが未整備な分、なんとかなった」
能登半島地震でも広範囲で上下水道が損傷。飲み水にも、トイレにも困ることに。
石川県能登町の避難所には、水洗のトイレトレーラーが全国から集められ、生活を何とか支えていました。
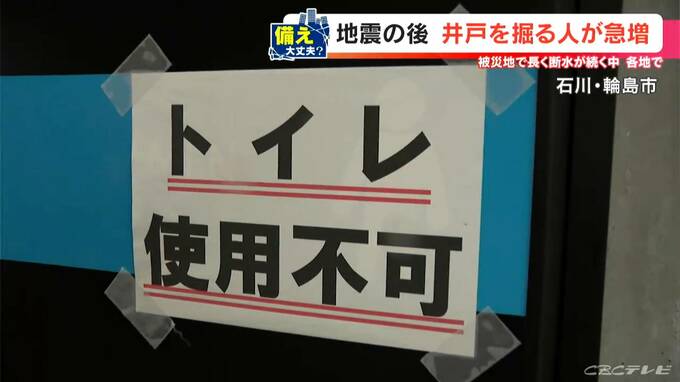

しかし、被災地では水に困らない集落も…
石川県輪島市の山あいにある、三井町です。


ここでは地区の住民が、昼間は倉庫で過ごし、夜はそれぞれ車中泊などをして避難生活を送っています。
(大石アンカーマン)
「顔の見える人が揃っているというのは、違うんでしょうか」
(住民)
「安心感がある。同じ思いをした人たちが近くにいて心強い」

彼らが避難所へ行かない大きな理由は…「水」。
地区のまとめ役で、市議会議員の門前さんの自宅へ行くと…

(大石アンカーマン)
「水は出ますか?」
(門前徹 輪島市議)
「水は出ます。普通に出ます」
門前さんの家では昔から「井戸水」を使っていて、地震直後からこの水を集落のみんなで共有していました。燃料はプロパンガスのため困らず、しばらくして電気が復旧するとみんなで風呂にも入っていました。

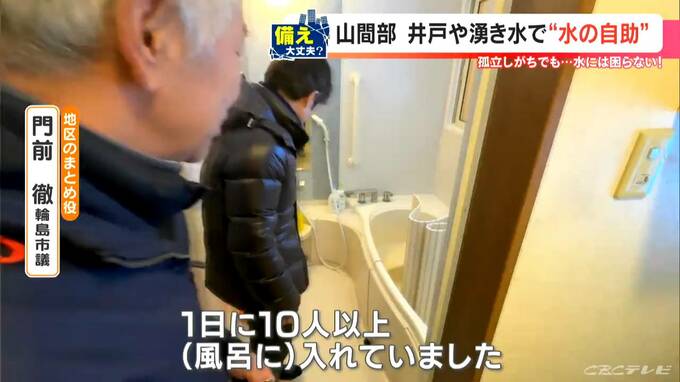
(大石アンカーマン)
「ここに村民の皆さん80人が?」
(門前徹 輪島市議)
「のべ人数で80人。1日に10人以上(風呂に)入れていました」
さらに…家の脇には山からの湧き水があり、これを汲んで集会所のトイレを流すのに使っていました。

この地区は、排水を地中に埋まっている合併処理浄化槽に流すため、下水管の損傷も関係なく水洗トイレが使えていたのです。
(門前徹 輪島市議)
「ありがたいことに凍結さえしなければ使えたので、トイレ環境は、よその避難所のように地獄ではなかった」

孤立しがちな山あいの集落が、実は水に困っていなかった現実。
(門前徹 輪島市議)
「田舎でインフラが未整備な分、なんとかなった」
(大石アンカーマン)
「都市化されていたら、もしかしたらダメだったかもしれない。中山間地のいいところでもあるのかもしれないですね」














