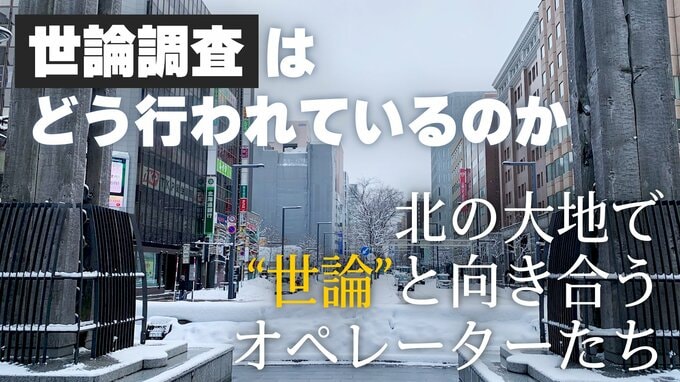定期的に行われる「世論調査」。実際に、誰が、どういった形で調査を行っているのか、みなさんはご存知だろうか。きょうはその内幕の一端をご紹介したい。
3月2日の土曜日。北海道・札幌市内は吹雪いていた。
この日、永田町では来年度の予算案を、年度内に成立させたい岸田内閣が、リミットである2日に衆院を通過させるため異例の“土曜国会”を行っていた。
※予算は衆議院を通過し、参院に送られた後「三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする」(憲法60条2項)という規定に基づき年度内成立を確実にするためには3月2日までに参院に送る必要があった。
こうした喧噪を離れた北の大地にある雑居ビルの1室でも週末とは思えない緊張に包まれた空間があった。
「JNN世論調査」が行われる現場に行ってみた
「世論調査は回答者の善意で成り立っている業務です。その善意ある人々に対して失礼の無い電話対応することで応えることができます」
ランドマークのテレビ塔が聳える大通公園から徒歩数分の距離に位置する高層のインテリジェンスビルの一角は熱気に包まれていた。女性のベテラン指導員の説明に真剣な眼差しで頷き、手元の資料をたぐり寄せる人々。
ここはJNNが月に1度行う定期世論調査を委託している調査会社の打ち合わせの様子だ。この日と翌日の2日間かけ、JNNでは世論調査を実施し4日(月)の朝ニュースから結果を報道する予定となっていた。
この調査会社では調査開始前に、実際に調査を行うおよそ60人のオペレーターとのミーティングに時間をかける。電話対応に関する留意点や、「なぜうちの電話番号を知っているのか?」「どういう目的で調査を行っているのか」など想定される相手方からの様々な疑問について適切に対応すべく指導する。こうしたミーティングを初日はまるまる午前中の時間を使って行われる。
JNNの世論調査は以下のような仕組みで実施される。
世論調査は「世論の縮図」を目指すことから性別、年齢構成など幅広に多様な人々の意見を反映させる必要がある。このためコンピューター上で数字を組み合わせた電話番号を作り発信する方法をとっている。これはRDD方法と呼ばれている。
また従来は自宅にある固定電話だけを対象にしていた時代が長く続いたが、携帯電話の普及とそれに伴う固定電話を持たない家庭が増えたことを踏まえ現在は固定電話50%、携帯電話50%の割合で調査が行われている。このためオペレーターも固定電話チームと携帯電話チームの二手に分かれて作業を行う。
午後2時 調査開始。
職場の空気は一変した。約60人のオペレーターは電話へのアクセスに注力する。
オペレーター➀「お休みのところ失礼致します。私はTBSテレビの調査を担当します・・と申します。ただいま週明けのニュースで放送するため、18歳以上の有権者の皆様を対象に電話による世論調査を行っております」
世論調査にとって第一の課題は相手の信頼を勝ち取ることだ。
いきなりの電話で「世論調査に協力を」と言われても「本当だろうか」と疑念を持つ人は多くいるだろう。また週末は多くの人々にとっては憩いのための貴重な時間となっている。実際に、今回の調査でも「いまから買い物に出かけなければいけないから」「いま孫たちが家に来ているので切らしてもらいます」などという回答が見られた。こうした厳しい状況下でオペレーターは限られた短い時間で正確に趣旨を伝え、協力をお願いすることになる。
オペレーター②「5分ほどで終わりますので是非、協力をお願い致します」
限られた時間で当方の趣旨を理解してもらうためにはやはり熱意と誠意が必要だ
多くのオペレーターのやりとりを傍らで聞いて、改めて原点を感じることができた。
また時間が経過するとともに固定電話と携帯電話のそれぞれの調査特有の難しさが浮き彫りとなってきた。