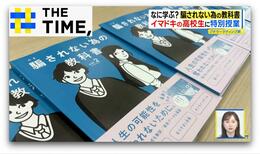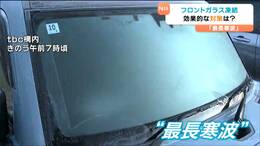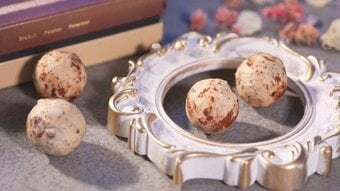元日に発生した能登半島地震では、富山県で予測よりも早く津波が観測された。
気象庁の津波到達予測時刻は地震から10分後だったが、実際に検潮所で津波が観測されたのは地震からたった3分後だった。
なぜ7分も早く津波が来たのか。その原因とみられているのが「海底地すべり」だ。
気象庁の予測システムや自治体のハザードマップにも含まれていない、この“想定外の津波”を津波研究の第一人者と再現した。
実験室で海底地すべりを人工的に起こすと、津波がどのように発生し、陸地に到達するのかが見えてきた。(TBS/JNN「Nスタ つなぐ、つながるSP 〜いのち〜」畑中大樹)
“想定外の津波” 実験で海底地すべりによる津波を再現
海の中で斜面が崩れる、海底地すべり。地震などによって海底地すべりが起きると、そこから津波が発生することがあるのだという。水中で地すべりが起こると水面はどのように動くのか、実験を行った。

実験に協力してくれたのは、津波研究の第一人者、中央大学理工学部の有川太郎教授。水槽に約100分の1スケールで海底を再現し、人工的に海底地すべりを起こした。

まずは比較的緩やかな斜面で海底地すべりを再現する。角度は約20度で、富山湾の海底にも同程度の勾配があるという。

斜面の砂がすべり出すと、勢いよくそのまま一気に崩れ落ちた。