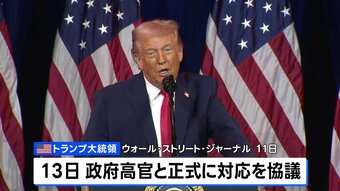半導体の世界シェアを落とした日本は「世界的な動きについていけなかった」“過去の教訓”を活かす
ーーー「かつて世界一だったレガシー」とおっしゃっていましたが、1980年代には日本の半導体世界シェアの半分以上を握っていたのに、なぜ、今苦境に立たされているのでしょうか。
野原諭局長:
政府側の問題と民間側の課題と両方あると思います。代表的なものを紹介しますと、日米半導体協定で日本の半導体メーカーが自由に販売価格を決められなくなったというのが一つ。それから、当時の批判によって日本が産業政策自体をかなりやめてしまったこともあります。民間の問題は、ビジネスモデルの変化ですね。かつて各日本の家電メーカーは垂直統合で、川上から川下の最終製品までを生産していたのですが、TSMCの創業者、モリス・チャン氏が新しいビジネスモデルを作られまして、製造と設計を分けてるビジネスモデルを生み出しました。そのような世界的な動きに対して日本は十分ついていけなかったといった課題もあったと思います。さらに、日本が産業政策をやらない間にですね、中国韓国台湾へ熱心に産業政策を展開されて、台湾は成功したところもあると思います。そういう意味で“過去の教訓”を活かして今回は取り組みを進める必要があると考えてます。
ーーーこの30年で世界的に半導体産業のあり方が大きく変わったということですね。
野原諭局長:
そうですね。1980年代日本が世界一だったときは主力の製品はメモリでして、しかも家電製品用のメモリでした。当時の日本家電メーカーは非常に世界的に強かったです。当時、日本の半導体メーカーはお客さんの日本の家電メーカーに向かってメモリー半導体を売っていたのですが、その後の主力製品が家電からパソコン、パソコンからスマホと変わってきまして、パソコンの先は、AIであったりサーバーであったり、自動車やロボティクスだと言われています。このスマホの次の需要もよく考えなければいけなくて、日本が世界一のときは川下のお客さんのところが日本国内にいたので日本は世界シェア50%だったんですけど、パソコンとかスマホになるとアメリカのお客さんになってアメリカのお客さんから、受注がもらえなかったので、シェアがどんどん落ちていったということですが、次のステージがAI、サーバー、自動車あるいはロボットなどになります。日本の半導体産業を育てていこう、強化していこうとすると、グローバルなアライアンスでよく考えなければならないと思っています。