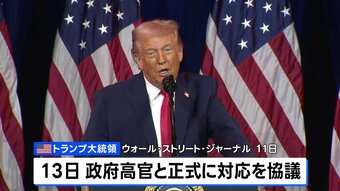「自国に供給拠点が無いと安定供給を受けられない」

ーーー先端ロジック半導体が今度不足する可能性があるとはいえ、日本で半導体を生産するTSMCは海外企業です。
野原諭局長:
3つある半導体政策の目的のうち将来の半導体不足に備えて安定供給を図り、日本経済、日本の産業に対して必要な半導体が供給されるという状況を確保していくことが一番重要で、そのときに、日本、日系企業でなければならないということはなくて、外資系の企業であっても日本国内に供給拠点ができることによって安定供給が図られるという面があります。実際グローバルにある半導体の種類が本当に不足すると、各国とも自国への供給が最優先になりますので、自国に供給拠点がないと安定供給を受けられない。そういうことにならないように将来に向けて備える必要があると思ってます。工場の計画から実際の量産開始まで3年ほどかかりますので、半導体不足が起きてからでは遅くて、早くからアクションをとらないと間に合わないということです。将来の需給の動向の見通しを立てつつ、不足しそうな分野については早めに手当をしていく必要があるだろうというふうに考えてます。
ーーー日本の半導体政策は、より有志国での連携に重きを置くようになってきているのでしょうか。
野原諭局長:
半導体は非常にサプライチェーンが長い産業でありまして、工程でプロセスで見ると1000ぐらいあると言われています。そのプロセスの全部を1か国だけで自給自足するのは現実的には非常に難しいというのが現実です。有志国、地域で連携して、お互いの強みを持ち合って、安定供給を図っていくことが基本的な考え方で、日本の強みである素材や製造装置については有志国に対して、供給責任を果たす必要があるわけです。ボリュームとして足りてる分野はそれで済むんですけども、絶対量が足りなくなると、それぞれ自国の供給を優先してしまいますので、有志国の中でも将来かなり厳しい半導体不足が予想される分野は自国内に供給拠点を持たないと、自国の供給が、確保できないということでありまして、先端のロジック半導体分野はその分野と国際的にも認識されています。アメリカもCHIPS法で最優先の投資分野は先端ロジック半導体です。ヨーロッパでもドイツがインテルとTSMCの工場の2社に2兆4000億円の補助金を投下しています。そこまでしているのはなぜかというと、この先端ロジック半導体分野が将来的に考えると供給が不足するであろうということが国際的な認識として共有されているので、各国ともに自国の供給を確保しなければならないという観点で投資をしています。日本についても、TSMCの1号棟と2号棟と投資を決定しましたが、これらは全部先端ロジック半導体であり、将来的に不足するということが予想されてるので、投資をしなければならないということです。
ーーー今回のTSMCの工場開所は、日本の半導体政策の大きな転換点になり得るでしょうか。
野原諭局長:
熊本の1号棟は支援を決定してから非常にスピーディに量産開始が見えてきていますので、スピード感は他のケースと比較すると早いと考えています。非常に重要なプロジェクトですが、半導体政策全体の中では一つのプロジェクトですので、この一つの工場だけで全てが解決するわけはありません。でも、非常に重要な一歩だとは思ってます。いろんな方々の貢献によって今日があります。まだ道半ばで全てが完成してるわけではありませんが、政策自体は進んでいるというふうに思っています。政策が成功するように全力を尽くしたいと思います。