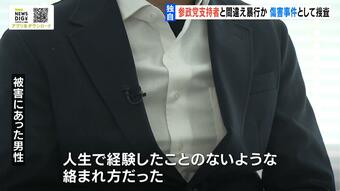『節電』ならぬ『節ガス』という言葉が、現実味を帯びてきました。
EUは20日、ロシアからの天然ガスの途絶に対応するため、加盟国にガスの消費量を過去5年間の平均と比べて15%削減するよう求める緊急計画案を公表し、フォンデアライエン委員長は「ロシアがガスを兵器として使っている」と強く批判しました。ロシアは、ロシアとドイツを結ぶ天然ガスのパイプライン『ノルドストリーム』によるガス供給を、6月から設備更新を理由に6割も削減し、次いで7月11日からは定期点検を理由にすべて止めるに至りました。定期点検は21日終わりましたが、再開されたガス供給は3割に留まる(つまり7割減!)という状態が続いている上、プーチン大統領はさらに減らす可能性にまで言及しています。色々と理由をつけてはいるものの、要するにロシアは、ウクライナ支援を続けるEU加盟国に揺さぶりをかけているわけです。
今は夏、しかも空前の暑さなので、ロシアからのガス供給が一時的に止まっても困りませんが、冬になれば暖房をガスに頼る欧州諸国は大混乱に陥ります。本来ならば夏のうちにガスの貯蔵タンクを満タンにしておきたいところですが、ドイツでは、こうしたロシアの『嫌がらせ』によって、貯蔵率が未だ60%に留まるなど厳しい冬への不安が高まっています。
ロシアによるウクライナ侵略開始から5か月、戦況が膠着する中、ロシアは少しでも国際環境を有利にすべく、切り札であるエネルギー資源を使って西側諸国の足並みの乱れを誘おうと必死なのです。ロシアはエネルギーの大輸出国ですが、5か月経ってわかったことは、中でも天然ガスが一番代替性の低い商品、逆に言えば、ロシアにとって最も強いカードだということでした。確かに、ロシア産原油の輸入禁止も欧州各国には痛手ではありましたが、原油は中東など他の国からスポットで調達することが比較的容易です。ロシア産の原油の大半は、結局、中国やインドなどが安い価格で購入することになったので、その分、中東の原油には供給余力ができました。さらには産油国がわざわざロシアから安い原油を買って、同じ量を市場価格で西側諸国に売ることで、利ザヤを稼いでいるという噂まであるほどです。地球全体で見ればでは需給がバランスしてくるのは、原油という商品が常温での貯蔵も輸送も容易で、それ故、流通市場が分厚いからです。
これに対して天然ガスは、液化にはマイナス163度という超低温が必要で、貯蔵や輸送のコストが高く、在庫が少ないだけに急に代替することは困難です。パイプラインはコストの安い輸送手段ですが、『ノルドストリーム』の例のように栓を閉められたら「はい、それまで」で、どこか別のところから受け入れたりはできません。ドイツも新たな調達先を探していますが、液化天然ガスの受け入れ施設を建設するのもこれから、という状況です。
ひるがえって日本も、『サハリン2』でロシアから脅しをかけられています。『サハリン2』からの天然ガスは日本の輸入量の9%を占め、半分は発電用に、半分は都市ガス用に今も使われています。もしも、これが止まるようなことになれば、冬のガス需給は一気に厳しくなります。このため日本政府は、電気と同じように『節ガス』要請や、最悪の場合には、ガスの使用制限ができる仕組みづくりの検討を始めました。『節電』に加え、『節ガス』まで求められたら大変です。
それでは、ロシアは本当に『サハリン2』から日本へのガス供給をすべて止めるのでしょうか?何をやるかわからないプーチン政権ですから、その可能性に備えることは、もちろん必要です。ただ他方、供給が続く可能性もあるかもしれません。ロシアにしても、中国に買い叩かれるより、日本になるべく有利な条件で売り続けたほうが良いと思うかもしれません。液化設備をはじめとする施設の運営上、日本を入れておくことが必要と考えるかもしれません。ならば、撤退の決断の前に、やれるだけ手を打っておくことも必要です。
確かに、この冬はヨーロッパにとっても、日本にとっても、ことのほか厳しい冬になりそうです。それでも、ロシアが揺さぶりをかけてくることがわかっているのであれば、こちらも備えをしつつ、相手の本音と条件を見極めて対応することが求められています。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
注目の記事
【札幌タイヤ脱落事故】父親が語る加害者への憤り 52歳男は執行猶予中に無免許運転で逮捕 裏切られた裁判所の温情と、終わらない家族の苦しみ 当時4歳の娘は意識不明のまま

住宅街脅かす“不明管”…40年放置の責任はどこに? 「富山県は間に何もはいっていない」消えた公社が残した“負の遺産”に市も県も把握せず

東北730% 北海道420% 花粉が去年より大量? 飛散ピークに現れる“おぞましい虹”の正体

血液不足の危機 若者の「献血離れ」はなぜ起きたのか?30年で激減した『最初の一歩』と消えゆく学校献血

大好物は「紙」4年前に国内初確認の害虫「ニュウハクシミ」急拡大で博物館が大ピンチ、1点モノの文化財を守れ!学芸員が突き止めた弱点で撲滅へ

日本列島ほとんど“真っ赤”に… 週末15日から“10年に一度レベル”の「かなりの高温」に? 沖縄以外の北海道・東北・北陸・関東甲信・東海・近畿・四国・中国・九州・奄美で 気象庁が「早期天候情報」発表