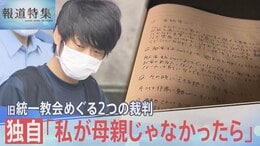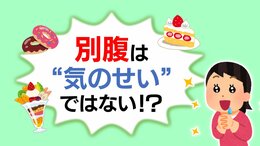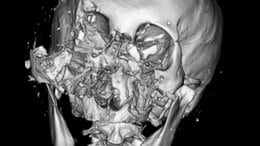経済は弱含みでも、日銀は「基調」で判断
ただ、実体経済は弱含みです。2月29日に発表された鉱工業生産指数は、ダイハツの不正を受けた生産停止もあって、前月比7.5%もの大幅マイナスとなりました。コロナ禍の20年5月以来の落ち込みでした。
民間の調査機関からは、24年1-3月期も実質GDPはマイナスになるのではないかという見方が出ており、そうなれば、日本経済は3期連続マイナス成長ということになります。しかも、賃金が物価に追いつかず、実質賃金はすでに21か月連続のマイナスです。
かねてから植田総裁は、ひとつひとつの指標より、経済の基調をどう見るかがより重要だと強調していますが、こうした中でも「好循環が始まっている」として、マイナス金利解除に踏み切った場合、賃金や物価の先行き、とりわけ実質所得がプラスに転じる時期や道筋を、どう判断したのか、きちんと説明することが求められるでしょう。
マイナス金利解除後の課題は山積
マイナス金利解除によって、短期金利は今のマイナス0.1%からゼロ%近傍になります。利上げ幅はわずか0.1%なので、影響は限定的なものにとどまるでしょう。その意味では、マイナス金利解除の是非や時期を論じるよりも、その後の課題にどう向き合うかを考えることの方がはるかに重要です。
マイナス金利解除の後、金利をさらにどこまで上げるのか、上げないのか。そして、長年、「念仏」のように唱えて来た、「2%の物価目標」を今後も続けるのか、もう少し柔軟性を持たせるのか。常態化した国債の大量買入れをどういうペースで、どの程度まで落としていけるのか。そして何より、財政負担増に直結する長期金利をこの先、どこまで市場に任せ、どこまでコントロールしていくのか。
いずれの課題も、簡単ではなく、かつ今後の日本経済のあり様を左右する大きな問題ばかりです。
「2%の物価目標」を金融政策の最優先課題(プライオリティー)に置いて、その実現まで「ひたすら緩和」するという、異次元緩和時代の金融政策の設計思想をどう変えるのかが問われています。
マイナス金利の解除は、そのスタートラインであり、オープンな議論が求められるゆえんです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)