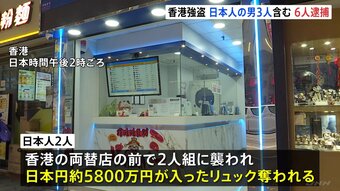戦後の奇跡が「日本ムラ」を正当化
バブル期の日本は、「不思議の国ニッポン」でした。
株主は、メインバンクなどの銀行や保険会社といった金融機関、系列や持ち合いによる事業会社が中心で、過半数がそうした「安定株主」でした。
「日本ムラ」にだけ通じる論理で株価が上がった時代です。
日本独自の会計制度をとり続け、今でいうガバナンスは機能しにくい構造でした。
バブルは、戦後日本の経済発展の「奇跡」の到達点でもありました。
東京が焼け野原になってから、わずか23年で世界第2の経済大国になり、約35年で「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とさえ呼ばれるほどの成功を遂げた国でした。
それ故に、当時の多くの人が「『奇跡の国・ニッポン』には、独自のやり方、システムがあるのだ」と信じていたとしても、それは責められることではありません。
「失われた」と呼ばれた30年間は、外から見て「理解不能」と思われたこと、ひとつひとつを、「当たり前」に変えることが迫られた時代だったように思えてなりません。
それは、グローバル経済の時代の必然的な帰結でもありました。
「稼ぐ力」で株価が上がる「当たり前」
過去の株価上昇局面では、経済危機など外的要因によって、最高値更新までには至りませんでした。
今回、株価が最高値を更新したのは、日本企業の稼ぐ力が向上しているからで、それを市場は素直に評価しています。
法人企業統計によれば、1989年に3.7%に過ぎなかった売上高経常利益率は、2023年には7.1%にまで上昇しました。
含み益で株価が上がったバブル時代とは、大きな違いです。
「稼ぐ力」の向上と並んで、配当工場や自社株買いで株主との向き合い方にも大きな変化がありました。
そこに「デフレ脱却」による成長加速という期待が加わったのが、今日の姿でしょう。
日本で未だ実現しない「世界の当たり前」
しかし、「稼ぎ」を人的資本(賃上げ)や国内設備投資に向ける比率は依然、低いままです。
2023年の企業の設備投資額は実額ベースで98兆円と、89年の85兆円からさして増えておらず、大企業の労働分配率は約55%と過去最低水準です。
「稼ぎ」を株主還元や内部留保にまわすだけではなく、前向きな投資振り向けて一層の生産性向上や競争力強化をめざすことは、世界の「当たり前」です。
その「当たり前」が実現しなければ、日本経済は「理解されない」事態に再び陥ることでしょう。
それは、物価と賃金が共に上がり、成長が一層拡大するという「好循環」の実現と、表裏一体です。
34年ぶりの日経平均株価の最高値更新によって、「バブル後」と呼ばれた時代は終わりを告げました。
しかし、新しい時代の到来に確信が持てるには、まだ至っていません。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)