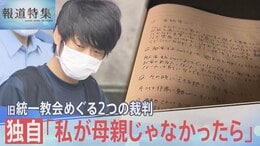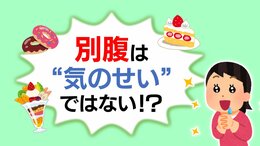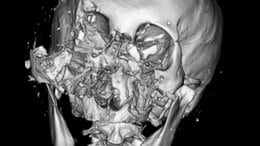株価は史上最高値更新が射程に
名目と実質で見え方の異なるGDPが発表された2月15日、東京株式市場では日経平均株価が終値でも3万8000円台に乗せ、いよいよバブル期の1989年12月につけた3万8915円という史上最高値の更新が射程に入って来ました。
「2期連続のマイナス成長なのになぜ株高?」と、違和感を指摘する声もあります。しかし、株価は名目値の世界です。物価を加味した実質値で株価の比較はしませんし、企業の売上げも利益も名目値です。名目成長率がこれだけ高ければ、株が上がって当たり前というわけです。
まずは名目成長を目指したのが「物価目標」
考えてみれば、「物価目標2%の実現」を優先した経済政策は、まず名目成長を目指した政策と、言い換えることができるでしょう。デフレでは成長のきっかけがつかめないという現実からスタートした政策だからです。
先に物価を上げて、賃金をそれに追いつかせ、追い越させることにつなげていくというのが、今狙っている「好循環」の具体的な経路です。それはなかなかの難路のようにも見えます。特に物価上昇率が2%をはるかに超えたこの1年は、賃金は物価に全く追いついていません。GDP統計でみるインフレ率(=デフレーター)は、2023年は3.7%でした。比較可能な1981年以降最も高い数字で、これだけインフレ率が高ければ、実質をプラスにするハードルは高かったと言えるでしょう。
「好循環」実現に向けた今後の政策こそ大事
春闘で去年を上回る賃上げを実現することは、最も重要なことです。しかし、それはスタート地点に過ぎません。実質賃金をプラスに反転させ、実際に消費支出が拡大し、その結果の需要増大を生産性向上につなげて、初めて「好循環」が実現するのです。
そのためには、円安是正を含め、高すぎる物価上昇をモデレートなものにすること。実質所得がプラスの領域に達するまでエネルギーなどの家計支援を続けること。可処分所得を減らすような政策を封印すること。需要増大が生産性向上を促す取り組みを続けることなど、課題は山ほどあります。
「昨年以上の賃上げ」は、決してゴールではありません。政策の手綱さばきが問われるのは、むしろこれからです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)