(ブルームバーグ):ローマに新規開業したノブ・ホテルは、「NOBU」ブランド特有の装飾を抑えたミニマルな美学で宿泊客を迎える。著名シェフ、松久信幸氏によるグローバルな事業展開の中でも、特に野心的な動きを示す最新施設の一例だ。
ノブの愛称で知られる松久氏(76)は試食や現地視察のために世界各地を飛び回りながら、世界有数の高級ホスピタリティー帝国を築き上げてきた。俳優のロバート・デ・ニーロ氏、映画プロデューサーのマイアー・テパー氏と共同で設立したノブ・ホスピタリティは、5大陸にわたり、58を超えるレストランと18のホテルを展開している。

拡大はなお続いている。現在進行中の新規プロジェクトには、アブダビ、モンテネグロ、ナッシュビルでの新施設が含まれており、慎重姿勢が強まる外食・ホテル業界の潮流に逆行する形で、攻めの世界展開を進めている。
競合他社の中には拡大ペースを落としたり、低価格志向の業態に軸足を移したりする動きも見られるが、ノブ・ホスピタリティは高級路線をむしろ強化している。2026年末までに少なくとも12件の新規プロジェクトを予定している。
非公開企業である同社の企業価値は、24年の株式売却後におよそ9億ドル(約1400億円)と評価された。
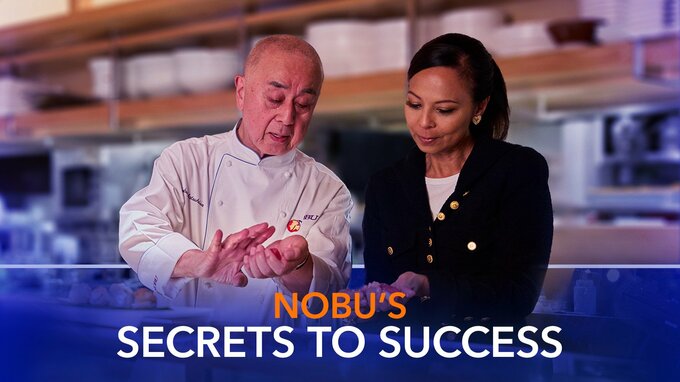
高価格帯の旅行市場拡大が見込まれているとはいえ、このタイミングでの拡張は大胆にも映る。ホスピタリティー業界はなお、旅行パターンや消費者の行動様式を大きく変えた新型コロナウイルス禍からの回復途上にある。
インフレで食材費や人件費は上昇し、サプライチェーンの混乱も続いている。旅行客は戻りつつあるものの、消費行動は読みづらく、ブランドへの忠誠心もかつてほどではなくなっている。
こうした状況下での事業拡張は、まさにハイリスクな賭けと言える。人々が今後も、親しみや憧れが融合した体験を求め、それに対価を支払い続けるという前提に立っているからだ。
NOBUというブランド独自の料理、デザイン、そしてセレブ性を組み合わせた魅力が、今後も客を引きつけ続けられるかが焦点となる。

松久氏は3月に来日した際、都内の自身のレストランでブルームバーグテレビジョンのインタビューに応じた。その前の週はフィリピンに滞在していたという。事業拡大の中でも、各店舗を年に2-3日ずつ訪れるようにしている。
レストラン事業からホテル、そして高級コンドミニアムへと事業を広げた同氏は独占インタビューで、世界中の美食家に対し、一貫した品質をどう維持しているのかを説明。
「心を込めて料理をすること。そうすれば人は笑顔になる」と語った。
こうした感情への訴えかけと精緻さの融合こそが、松久氏のキャリアを特徴付けてきた。
埼玉県生まれの同氏は8歳の時、父親を自動車事故で亡くしている。建築家の家系で、同じ道に進むことを期待されたが、学校に入っても好きになれなかったという。
料理人としてのキャリアは新宿のすし店で始まったが、食への関心は子供の頃からあった。当時は自室が台所の隣で、「台所の音と匂いで目が覚めた」という。「自分では決してやらなかった」が、母親や祖母が料理するのを「いつも見ていた」と述べた。
伝統的な和食を学んだ後の1972年、都内で親しくなった日系ペルー人の顧客と首都リマで店を開くという新たな挑戦に踏み出した。現地で入手できる日本の食材は限られ、しょうゆと唐辛子、刺身と香菜を組み合わせるなど、工夫を強いられた。
ペルーは日本からの移民を早くから受け入れた国の一つで、現地の食材と日本の技法を融合させる試みが進み、「ニッケイ料理」と呼ばれる食文化が生まれた。リマでの経験は松久氏の後のスタイルを形成する重要な時期となったが、当初は試行錯誤の連続だった。
共同経営者とは決別することになり、アルゼンチンで短期間働くと、松久氏は日本に戻った。その際、米アラスカ州アンカレジでレストランの開業を予定していた役者と出会うが、1977年に開店して成功を収めてわずか50日後、この店は火災で全焼した。人生で最も沈んだ時期となり、命を絶つことさえ考えたと同氏は振り返る。
「アラスカでの経験は最悪だった。でも、あの経験がなかったら今の自分はないかもしれない。多くを学んだ」と語った。
こうした話をしながら松久はすしの「正しい」食べ方を見せてくれた。わさびは「シェフが既に最適な量を入れて」握っているので、付け足す必要はないと説明する。
さらに、シャリを成形する独自の6段階の手順を披露。やがてカウンターには、深紅のマグロ、透き通るような鯛、紙のように薄く切られたイカ、そしてセビーチェ(生の魚介類をレモンやライムの果汁でマリネし唐辛子などで味付けしたペルー料理)の皿が並んだ。

多くの食通にとって、松久氏による洗練されたニッケイ料理こそが、このジャンルとの出会いだった。同氏は1987年、再び勝負に出てロサンゼルスに小さなレストラン「マツヒサ」を開いた。ここから、フュージョン料理の概念が静かに塗り替えられていくことになる。
地元産のタラを酒とみそのブレンド液に漬け込み、安価でありふれた魚を静かな完璧さをたたえる一皿へと変貌させた。この「ブラックコッドの味噌漬け(Black Cod Miso)」は、やがてノブの代名詞となり、世界的なトレンドを生み出した。
カリフォルニアの客たちはこの料理を愛した。その中には常連客のボブという人物がいた。この人物はやがて、ニューヨーク進出を勧めるようになった。
「何をしている人か知らなかった。映画も見ないので。だから『ありがとう、ボブ。でも結構です』と断った」という。
ボブ、すなわち俳優のロバート・デ・ニーロ氏は諦めなかった。同氏の友情とビジネスセンスが、その後の松久氏の人生を大きく変えることになる。
1994年、2人に映画プロデューサーのテパー氏が加わり、ニューヨークのトライベッカ地区に初めて「ノブ」レストランがオープン。瞬く間に人気を集めた。
控えめな共同経営として始まった取り組みは、やがて世界的ブランドへと成長した。ホテル事業への進出はデ・ニーロ氏の発案で、それから30年後の現在、NOBUの名を冠したホテルとレストランが世界各地に展開されている。
同社ウェブサイトには、世界各地で開業予定のホテル兼レストランが数十件並んでいる。本拠地の米国でもブランド体験をライフスタイル分野に広げる戦略が進んでいる。最近ではマリブのノブ旅館(Nobu Ryokan)でウェルネス分野のパートナーシップを開始。ホスピタリティーの枠組みに包括的な健康と長寿の要素を取り入れている。
NOBUの全レストランとホテル、そして今では全てのレジデンスが、同じ理念にのっとっているという。その一貫性を確かめるため、松久氏は世界を飛び回っている。
「全て、同じやり方でやる。NOBUのコンセプトは、心だ」。
原題:Nobu Expands Globally as De Niro and Matsuhisa Bet on Luxury(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.com/jp
©2025 Bloomberg L.P.
















