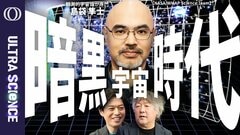今後の米中関係…日本は「代理戦争に巻き込まれぬよう注意を」
Q.アメリカのトランプ大統領がアジアを歴訪します。今後の米中関係をどう見ますか?
楊伯江 所長
高市氏は2022年に安倍晋三元総理が銃撃されたあと自らを「安倍路線」の継承者であると位置付けてきました。「安倍路線」とは何なのでしょうか?高市氏が明確に示している点は2つあると思います。1つは積極財政を主張していること。もう1つは歴史問題に対する姿勢です。ただし注意すべきなのは、安倍元総理が憲政史上最長となる任期のなかで、内政と同時に重要な隣国との関係を発展させることに注力していた点です。そこには中日関係も含まれます。ロシアとの関係改善も積極的に模索していました。現在の日本の行政指導者は「安倍路線」を継承するのでしょうか?それとも一部分だけを継承するのでしょうか?これはリーダー個人の認識の問題だと思います。
アメリカについてですが、この国は中日関係を考えるときとても大きな存在です。アメリカは非常に実用主義的な文化を持っています。現実の利益のために素早く態度を変えます。アジアの隣国であり世界の主要な経済体でもある中日両国は、他国の駒になり、代理戦争に巻き込まれないよう警戒すべきです。代理戦争は日本の政治家が考えるべきとても重要な問題です。
中国とアメリカの関係ですが、私は冷戦時代におけるアメリカとソ連のような関係にはならないと考えています。トランプ政権が誕生してから私たちはトランプ大統領のことを反グローバリズムだと指摘してきました。しかし、トランプ大統領が好むと好まざるとに関わらずグローバル化は長期間にわたって維持され、多くのものが積み重なってきています。このような状況では重要なカウンターパートに対して戦争のような極端な手段をとることはできません。人の交流や経済関係は双方にとって人質のようなものです。ですので、中米関係は冷戦時代における米ソ関係のようにはならないと思います。
ただ、注意しなければならないのは、40年を超える冷戦の期間中、アメリカとソ連の間で直接戦争になることはありませんでしたが、両国の支援のもとで多くの代理戦争が起きた点です。代理戦争の舞台になった国は非常に哀れであり、これは時代の背景によるものです。
また、中国の戦略文化がソ連やロシアとは異なるということもしっかりと理解すべきです。例えば、ソ連やロシアは問題を解決する際に武力を行使するハードルが比較的低いのです。一方でアメリカの研究者から多く寄せられる質問も「中国と日本はいつ、どの海域で衝突し戦争に突入するのか」といったものでした。私たちは武力による問題の解決は想定していませんでした。これは中国とアメリカの戦略文化の違いを反映していると思います。

「日本の政党政治は再検討が必要」今後の日本政治 中国側の注目ポイントは?
楊伯江 所長
高市内閣の登場は日本政治の進歩なのか自民党の派閥政治による堕落なのか、最近の日本政治を考えるうえで研究に値するテーマだと思っています。憲政史上初の女性総理の誕生はかつてない出来事であり、注目し祝福すべきだと思います。ただ、高市氏に女性ならではの主張はなかなか見られません。今回の自民党総裁選での最終的な勝利は派閥によるコントロール、派閥政治によって生まれたものだと思います。麻生太郎副総裁が生み出した傑作であることは明らかです。
日本が採用している間接選挙制度では、議員が党総裁を選び、総裁が党を代表して総理指名選挙に臨みます。議席を最も多く持っている政党のリーダーが総理になる可能性が高いです。ですので、総裁選がはじまったときから有権者にとっては関係がなくなるのです。有権者の影響を受けることはなく民意の束縛からも解放されることになります。最後には数字のゲームになってしまうのです。これは、いち政権や自民党総裁の責任ではありません。戦後の保守政治の責任だと思います。
そして、私が注目しているのは今や老舗の政党は機能していないということです。日本共産党や社民党、自民党、公明党といった老舗の政党は機能していません。おそらく時代遅れになってしまったためで、参政党や日本維新の会といった政党が多くの注目や支持を集めています。
どのような政治構造、政治文化が今日の日本に合っていて、国をより明るい未来に導くことができるのか?日本の政党政治は再検討が必要な段階に来ているのだと思います。日本がより良く発展することを願っています。そうであれば、中日関係もより明るい展望が開けるでしょう。
(インタビューは10月23日)
楊伯江 氏
中国社会科学院日本研究所 所長
中華日本学会 会長
日本国際フォーラム客員研究員やハーバード大学訪問研究員などを歴任。
聞き手 JNN北京支局 松尾一志