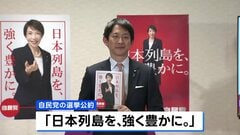(ブルームバーグ):米大リーグのワールドシリーズに野球界のトップスターが勢ぞろいするとは限らないが、今年は一人、際立つスーパースターがいると多くのファンは認めるだろう。
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平だ。ナショナルリーグ優勝決定シリーズ最終戦では、投手として6回を無失点に抑える一方、打者として3本の特大本塁打を放つという大リーグ史上でも屈指の個人パフォーマンスを見せつけた。
野球の統計に興味がない人でも、大谷の経済的な影響力を見れば、そのスター性は明らかだ。ドジャースとの契約は10年で総額7億ドル(約1070億円)。
巨額だが、ドジャースはチケットやグッズ販売、日米を中心とするスポンサー契約の広がりで、わずか2シーズン足らずでその投資額を回収した。つまり7億ドルでさえ、大谷が生み出す収益と比べれば割安と言える。
大谷の驚異的な成功は、フィールド上の活躍でも、収入面でも、移民が米経済にもたらす恩恵のうち、最も重要でありながらあまり認識されていない側面の一つを鮮やかに浮かび上がらせている。
1世代前には、大谷のような経済的リターンを生み出せる選手はいなかった。しかし、幾つもの要因が重なった結果、今日のスーパースターはより高い価値を持つようになっている。この傾向は野球に限らず、経済全体にも当てはまる。
スーパースターの存在価値は、報酬に表れている。ヘッジファンドの高成績マネジャーは年収30億ドルを超え、テイラー・スウィフトは35歳で純資産10億ドル超の資産家となった。人工知能(AI)のエリート研究者は年間2億5000万ドル以上の報酬を得ることもある。
こうした超一流人材の多くが移民だという点は、見落とされがちだ。「フェイスブック」や「インスタグラム」を展開するメタ・プラットフォームズは、新設のスーパーインテリジェンス研究所に世界有数のAI研究者11人を採用したが、全員が移民だった。
マッカーサー財団の「天才賞」受賞者のうち20%以上が移民で、米国の人口に占める移民比率(13%)を大きく上回る。化学・医学・物理学のノーベル賞受賞者の約40%も移民出身だ。
2022年時点で最も企業価値が高かった米国の非上場ベンチャー企業4社(スペースX、ストライプ、インスタカート、データブリックス)は、いずれも移民が創業した会社だ。
多様性
理由の1つは明白だ。地球上の人類のほぼ96%は米国以外に住んでいる。だが、より本質的な理由は、スーパースターのパフォーマンスにまつわる数学だ。
ビジネススクールの研究者アーネスト・オボイル・ジュニア、ハーマン・アグイニス両氏は、産業全般で業績が「べき乗則」に従って分布していることを示した。
つまり、大多数の従業員による業績は比較的低い水準に集中している一方で、ごく少数の人材、いわばスーパースターが突出して高い成果を上げているということだ。
こうしたスーパースターの業績が極端になるほど、組織全体のパフォーマンスは彼らによって左右されるようになる。言い換えれば、平均的な従業員の能力よりも、スーパースターがどれだけいるかのほうが重要になるということだ。
「ブラック・スワン」などを執筆した投資家ナシーム・タレブ氏は、そうしたハイパフォーマンスの例外的人材を見つける可能性を最大化するためには、できる限り多様性を育むべきだと指摘している。
移民の受け入れは、まさに彼らが米国とは異なる環境から来たという理由で、分散(ばらつき)を高める最も手軽な手段だ。移民は異なる教育や異なるトレーニングを受け、異なる考え方や文化に触れている。
大谷のケースはその好例だ。米大リーグでは、キャリアを始める選手が打者と投手の両方を務めることは認められなかった。大谷がそれを実現できたのは、日本出身だからだ。
大谷は高校を卒業してすぐに米大リーグに行くのではなく、二刀流を認めた北海道日本ハムファイターズに入団することを選択。やがて投打で驚異的な実力を示したことで、大谷は米国の球団に対しても、大きな交渉力を持つようになった。
大谷が米大リーグで唯一無二の存在となったのは、超人的な才能に加え、移民という立場が生んだ独自の背景によるところも大きい。
もし米国がAIや科学、あるいは現代経済のあらゆる分野で世界をリードし続けたいなら、スーパースターが必要だ。そしてスーパースターを得たいなら、移民を受け入れるべきだ。大谷はそのことを、野球という舞台で雄弁に語っている。
(ゴータム・ムクンダ氏は企業経営やイノベーションなどを研究し、エール大学経営大学院でリーダーシップ論を教えています。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Ohtani Is an Economic Superstar. He’s Not Alone.: Gautam Mukunda(抜粋)
コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:New York Gautam Mukunda gmukunda2@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Kristen Bellstrom kbellstrom@bloomberg.netもっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.