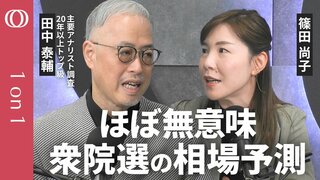(ブルームバーグ):楽天グループやソフトバンクグループなど、事業会社による劣後債の発行が相次いでいる。負債でありながら一部は資本として扱われるこの「二刀流」の社債は、格付け対策や株式価値の希薄化回避の手段として定着しつつある。企業財務の柔軟性を高める仕組みとその狙い、そして投資家が注目すべきポイントを解説する。
Q1:劣後債ってなに?
劣後債とは、企業が万一破綻した場合に元本などの返済の順番がほかの債務より「劣後」する、つまり後に回る債券だ。返ってくるのは最後。その分、投資家は高い利回りという報酬を得る仕組みになっている。
Q2:なぜ事業会社が劣後債を発行する?
一般の事業会社がなぜわざわざ高い利払い費用を払ってまで劣後債を発行するのか。理由は大きく2つある。
まず、格付け会社が調達額の一部を資本と認定するため、株式発行による希薄化を避けながら資本性資金を確保できること。そして、財務の安定性を対外的に示せることだ。
劣後債は企業にとっては借金だが、一部は格付け上の資本として扱われる。株と社債の中間的な存在だ。株式は希薄化せず、格下げリスクも抑えられる。この二刀流の効果から、業界では「ハイブリッドボンド」とも呼ばれる。
Q3:登場したのはいつ?
かつては規制対応で自己資本を増やす必要があった金融機関の専売特許だったが、超低金利の時代に企業も新しい資金調達の道として活用機会を探り始めた。2015年、三菱商事が事業会社として初めて劣後債を公募で発行し、19年には発行総額が1兆円を超えるまでに拡大した。
Q4:ニュースで見かける「NC」ってなに?
「NC」はノンコール(Non-Call)の略で、発行体が一定期間は債券を償還(コール)できないことを指す。
劣後債の最終償還年限は一般的に普通社債より長めで、永久劣後債という満期がない債券も存在する。とはいえ実際には企業はあらかじめ設定したノンコール期間が過ぎた後に繰り上げ償還することがほとんどだ。
例えば「NC5」なら、発行から5年間は償還できず、6年目以降に企業の判断でコールできる仕組みだ。市場では「初回コールまでの期間=実質の年限」と見なされる。そのため楽天Gの永久劣後債も、ソフトバンクGの期限付き劣後債も、ノンコール期間が5年前後であれば市場では同じ5年ゾーンの債券として値決めされる。
Q5:コールしないとどうなるの?
市場では多くの投資家が初回コールで償還されると見込んで価格をつけるため、永久劣後債であっても「実質5年債」として取引されるのが一般的だ。このため発行体がコールを見送ると、その後の利払いが上昇する「ステップアップ(利回り引き上げ)」条項が設定されているケースが多い。
この条項は経済的にもリファイナンスを促す仕組みとなっており、コールを見送ると、資金繰りが厳しいのではないかとの見方を招きかねない。こうした理由から、多くの企業は初回コールでの償還を選ぶのが実情だ。
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.