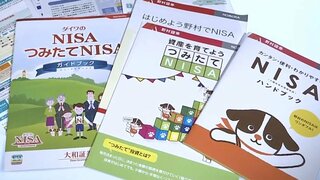(ブルームバーグ):どのゲーム機が優れているかを巡り、学校の校庭やオンライン掲示板などあらゆる場所で何十年にもわたって激しい論争が繰り広げられてきた。
任天堂の「スーパーファミコン」やセガの「メガドライブ」の時代から「プレイステーション(PS)」や「Xbox」に至るまで、各社は自社陣営に消費者を引き込むために数億ドルを投じ、ファン同士は相手ブランドのユーザーにあまり上品でない呼び名を付け、対抗意識を抱いてきた。
だが、その長きにわたる「家庭用ゲーム機戦争」に終止符が打たれるかもしれない。米マイクロソフトが、Xboxの代名詞とも言えるシューティングシリーズ「Halo(ヘイロー)」を、ライバルであるソニーグループのPS向けに提供すると発表したのだ。
マイクロソフトとソニーは四半世紀にわたり、業界支配を巡って「カミソリと替え刃」のビジネスモデルで競ってきた。
つまり、マイクロソフトのゲーム事業トップが2022年に明かしたように、ハードウエアについては、しばしば1台当たり100-200ドル(約1万5400-3万900円)を自社負担するような価格で販売し、利益はその後のソフトウエア販売で確保するというものだ。
ユーザーを囲い込むため、マイクロソフトもソニーも自社機でしか遊べない専用タイトルを作り続けてきた。Haloはその象徴的な存在で、01年の初代Xbox登場時からブランドの代名詞となった。マイクロソフトがソニーや任天堂に挑戦する上で不可欠な存在だった。
米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)によれば、HaloのPS登場は「ディズニーがミッキーマウスをユニバーサル・スタジオに貸し出すようなもの」だという。
それどころか、DCコミックスのヒーロー、バットマンがマーベルのアベンジャーズに加わる、あるいは、FCバルセロナなどで活躍したリオネル・メッシがレアル・マドリードでプレーする、コカ・コーラが自販機でペプシを売るようなものかもしれない。
このニュースを受け、株式市場でミーム銘柄として知られるゲーム小売り大手ゲームストップは、ゲーム機戦争の終結を宣言。そのメッセージはホワイトハウスまでもが人工知能(AI)による生成画像で拡散した。
トランプ米大統領がHaloの主人公マスターチーフに扮し、「Power to the Players(プレーヤーに力を)」との文言を添えた画像が投稿されたのだ。有害な分断を招く「部族主義」が日常生活の隅々にまで浸透している今の時代に戦争終結となれば、ちょっとした皮肉だ(もっとも、トランプ氏はずっとノーベル平和賞を狙っている)。
テクノロジーの進化
実際には、この戦いはすでに終息に向かっていた。マイクロソフトはすでに「Gears of War」や「Forza」などの自社人気タイトルをPSで展開しており、定額で多くのゲームで遊べるサブスクリプションサービス「ゲームパス」への誘導を強化している。
さらにここ1年、Xboxは専用ゲーム機に限らないとして、スマートフォンやノートパソコン(PC)、スマートテレビなどあらゆる端末をXboxタイトルのプレー対象とする構想を打ち出している。
背景にはテクノロジーの進化がある。かつては独自のハード構造を持っていたゲーム機だが、今ではPSやXbox、そして中級のゲーミングPCとの間に大きな差はほとんどない。
これにより、業界の従来型ビジネスモデルは、ストリーミング時代におけるビデオレンタルのように時代遅れになる可能性がある。
ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)は、クラウドゲームやモバイル画面、生成AIにより「専用ハードでゲームをすることが、やがて大多数のプレーヤーにとって時代遅れに感じられるようになるだろう」と予測している。
ただし、クラウドゲームの台頭予想はこれまで何度も外れており、グーグルの親会社アルファベットは自社のクラウドゲームサービス「Stadia」を終了すると22年に発表した。不人気だったのだ。
Xboxにとっての課題は、この新たなビジネスモデルを本気で信じているのか、それとも生き残るためにやむを得ず方向転換したのか、という点だ。
マイクロソフトは2000年代半ばから後半にかけて「Xbox 360」で業界を席巻したが、その後はPSだけでなく、「スイッチ」で復活した任天堂にも後れを取っている。ブルームバーグ・ニュースによれば、マイクロソフトの経営陣はXbox部門に業界平均を上回る野心的な利益率目標を課している。
ソニーも試行錯誤を続けている。代表的なPS向けタイトル「Spider-Man」や「The Last of Us」はPC向けにも展開している。吉田憲一郎会長は24年のインタビューで「コンピューティングがあるところならどこでも、ユーザーはお気に入りのゲームをシームレスにプレーできるようになる」と語った。
ソニーは人気シューティングゲーム「Helldivers 2」もXbox向けにリリース。世界で最も閉じたデジタルエコシステム(生態系)を持つ米アップルでさえ、「アップルミュージック」や「アップルTV」をグーグルの基本ソフト(OS)「アンドロイド」搭載端末などで提供している。
ゲーム機とPCの境界が曖昧になる中で、専用ハードの存在意義が薄れつつある。
もっとも、業界の潮流を読むのは難しい。10年前、投資家らは任天堂にハード事業から撤退して、モバイルゲームへ移行するよう迫った。だが、同社はこれを拒み、スイッチの世界的ヒットによって大成功を収めた。
Xboxが全てを牛耳るようなことになれば、むしろユーザーのXbox離れを招く危険性もある。ゲーマーが「エピックゲームズストア」や米バルブの「スチーム」など他のオンラインストアに流れることを誰が止められるだろう。
いずれ、次世代のファンたちはどのオンラインストアを使うかで言い争う時代になるかもしれない。ゲーム機戦争は終わっても、ユーザーの対抗意識には終わりはない。
(リーディー・ガロウド氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、日本と韓国、北朝鮮を担当しています。以前は北アジアのブレーキングニュースチームを率い、東京支局の副支局長でした。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Console Wars End Not With a Bang, But a Whimper: Gearoid Reidy(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.