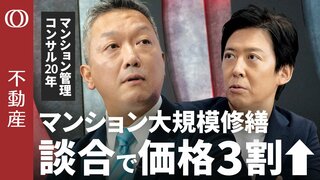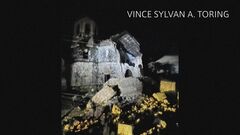(ブルームバーグ):ソニーグループの金融完全子会社であるソニーフィナンシャルグループ(FG)が29日、東京証券取引所プライム市場に上場した。初値は205円と参考値段を37%上回り、終値でも参考値段を超えた。新株発行や公募、売り出しを伴わない直接上場(ダイレクトリスティング)で、2000年以降で初めての事例となった。

ソニーFG株は買い気配で始まり、午前10時過ぎに売買が成立。一時は210円を付ける場面もあったが、その後株価水準を切り下げ、173.8円で上場初日の取引を終えた。初値決定での気配値の基準となる流通参考値段は150円だった。上場時の発行済み株式総数は71億4936万株で、終値を基にした時価総額は約1兆2400億円規模となる。
ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、スティーブン・ラム氏は参考値段比で上昇したことについて、主に生命保険事業による利益成長に対する期待感の表れだと分析。最大で1兆9000億円の時価総額になると予想した。
ソニーGは23年度の税制改正で認められた「パーシャルスピンオフ」という制度を利用し、20%未満の株式を継続保有しつつ、残るソニーFG株を株主に分配した。ダイレクトリスティング方式は通常の新規株式公開(IPO)と違い、証券会社の株式引き受けを伴わないため、引受手数料などの上場コストを抑えられ、準備期間も短縮化しやすい。東証の資料によると、国内では杏林製薬が1999年に実施した。
東証や政府が企業に対しコーポレートガバナンス(企業統治)の向上や事業ポートフォリオの見直しを促す中、ソニーFGのスピンオフ(分離・独立)上場は事業再編での新たな選択肢の一例となる。異なる事業を複数手掛けることで企業価値が割り引かれる「コングロマリット・ディスカウント」の解消にもつながる可能性があり、隠れた内在価値の顕在化をもたらすかに注目が集まる。
調査会社のストック・スピンオフ・インベスティングの創業者、リチャード・ハウ氏は「映画やゲーム、音楽、半導体を手掛ける企業が金融サービスまで抱える必要はなく、非常に合理的な取り組みだ」と評価。今回のスピンオフが「ソニーGの複合企業から複数の単一事業企業へ移行する第一歩であれば望ましい」と話した。
三菱UFJアセットマネジメントの友利啓明エグゼクティブファンドマネジャーは、企業は資本コストを意識した経営が求められる中、スピンオフ上場の事例が今後も増える可能性があるとの見方を示す。
需給の重し
上場後の株価動向を巡っては、指数に関連した需給が重しになるとみられている。ソニーFGは上場日の29日に日経平均株価の算出対象に加わり、翌30日に除外される。このため、29日終値では指数に連動した運用を行うパッシブファンドなどから発行済み株式の1.7%に相当する1億2500万株の売りが発生すると、大和証券の橋本純一チーフクオンツアナリストは推測した。
三菱UFJアセットの友利氏も、短期的には指数関連やソニーFG株を受け取った一部アクティブファンドの売りに加え、ソニーFGによる自社株買いなど需給要因で株価が左右される状況が続き、適正価値を判断しづらいとみている。
ソニーFGは金融株でありながら、構造的に金利上昇が逆風になりやすいとの指摘もある。傘下のソニー生命保険は、将来の保険金支払いに備えた超長期債の保有が過大な「オーバーヘッジ」状態にあり、超長期債の利回りが上昇(価格は下落)すると含み損が膨らみ純資産が毀損(きそん)するため、株主にとってネガティブだとSMBC日興証券の村木正雄シニアアナリストは分析する。
一方、ソニーFGのトップライン成長は株価にとってプラスとなり得る。同社では26年3月期の純利益は820億円と、前期比4.1%増を計画している。SMBC日興の村木氏は、生保・損保・銀行のトップライン成長は投資家から評価されやすいと指摘した。
ソニーFGの遠藤俊英社長は25日に開いたメディア向け説明会で、これまではソニーGしか「モニターする株主はいなかったが、これからはおそらく30万社・人以上の株主に見られ、厳しく批判される」と述べた。生保や銀行など傘下の会社が連携して「新しい価値を作っていかなければいけない」とし、「そこが問われる局面になっている」と語った。
(リードと2段落の株価変動や数値を更新します)
--取材協力:佐野七緒.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.