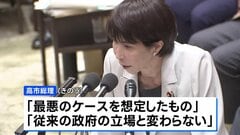(ブルームバーグ):トランプ米政権の関税措置や対外援助削減、ビザ(査証)関連の制限などの政策により米国の東南アジアにおける影響力が低下し、中国が支配的な存在として一段と認識されるようになっている。オーストラリアのシンクタンク、ローウィー研究所がこう指摘した。
シドニーを本拠とする同研究所は24日に発表した「東南アジア影響力指数」で、米国を域外パートナーとして中国に次ぐ2位に位置付けた。
米国の外交姿勢を「継ぎはぎ」と表現する一方、中国は貿易・投資・外交を一貫して展開し、地域での存在感を確固たるものにしていると分析している。
貿易・投資・防衛の観点から各国との関係を評価したリポートによれば、「中国は東南アジアの至る所で存在感を示している」が、「対照的に米国は東南アジアで二面性を見せている」という。「トランプ政権の関税や援助削減、国際教育政策は、米国とこれらの国々とのすれ違いを一層深める可能性が高い」と警告した。
中国は地域貿易を支配しており、東南アジアからの輸出の20%を取り込み、輸入の26%を供給しているが、米国の比率は16%にとどまるとリポートは説明。カンボジアとラオス、ミャンマーでは、中国の影響力は米国を60-150%上回るという。
米国の影響力が最も強いのはフィリピンやシンガポールといった伝統的な同盟国で、防衛関係が中心だ。しかし大陸部の東南アジアでは、米国は次第に周縁的な存在と見なされつつあるという。
リポートによると、中国は貿易・投資・外交を通じ、かつて米国が支配していた地域で影響力を広げている。また、東南アジアの各国も単一の大国への依存を避け、地政学的リスクを抑えるため分散化を進めているという。
ローウィー研究所の副リサーチディレクター、スザンナ・パットン氏は調査結果を踏まえ、「中国は米国を明確に上回っている」とコメント。「同時に、東南アジアの国々の間で隣国との関係の重要性も示されており、中国が地域を完全に自国の影響下に置いているわけではない」と付け加えた。
原題:Trump Weakening US Clout in China’s Backyard, Report Warns (1)(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.