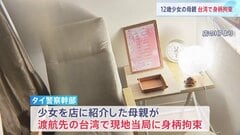(ブルームバーグ):米国の上場企業は半世紀以上にわたり四半期ごとに決算を公表してきたが、トランプ米大統領は15日にSNSへの一連の投稿で、この慣行に再び異議を唱え、長年の議論を再燃させた。
トランプ氏は、上場企業の決算報告を現行の四半期ごとから半年ごとに切り替えるよう求め、企業が「経費を節約でき、経営陣は適切な会社運営に集中できる」と指摘した。
2018年にもトランプ氏は、世界の著名経営者との議論を引き合いに出して半年ごとの決算報告制を支持し、柔軟性の向上やコスト削減につながると発信していた。
TDカウエンのアナリスト、ジャレット・サイバーグ氏は、米証券取引委員会(SEC)が半年ごとの報告に切り替える可能性を60%と見積もる。一方でウォール街では、実現には懐疑的な声も多く、説明責任の低下や変動性上昇のリスクを指摘する声もある。
四半期ごとの決算報告は、1929年の株式市場暴落を受けた透明性向上の取り組みの一環としてSECにより70年に義務付けられた。
市場関係者の意見を以下にまとめた。
◎ジャレット・サイバーグ氏(TDカウエンのマネジングディレクター)
「SECのアトキンス委員長にとっては、大統領に成果として示しやすい政策だ。規制緩和路線にも沿う。四半期から半年ごとへの切り替えは、不可能ではなく可能性が高まったと見ている。ただ、提案を策定し、司法審査に耐える経済データを集めるには少なくとも半年かかるだろう」
◎アイリーン・タンクル氏(BCAリサーチのチーフ米国株ストラテジスト)
「ストラテジストとして、私は決算発表の分析や四半期ごとの成長の追跡に力を注いでいる。しかし、四半期ごとの報告は、洞察を提供するよりも、予想を操るものになってきている。8割近くの企業が四半期ごとに予想を上回っているため、ガイダンスの信頼性は低下しており、短期的な目標を達成しなければならないというプレッシャーが、経営判断をゆがめている。また、高コストな報告義務は米国市場の株式離れを助長している。透明性とデータは重要だが、報告頻度を減らすことが米国企業にとって最終的には健全な選択となり得る」
◎サラ・ビアンキ氏(エバコアISI シニアマネジングディレクター)
「トランプ氏が短期的に強く推す可能性は低く、アトキンス氏は通常のSEC手続きを進める余地があるとみている。アトキンス氏自身が既に大統領のSEC指揮権を認めている事実が一因だ。実際のプロセスを経てアトキンス氏ら委員が別の方策が妥当と考えた場合に真の試練が訪れるだろう」
◎ジョナサン・ゴラブ氏(シーポート・リサーチ・パートナーズのチーフ株式ストラテジスト)
「資本市場と米経済は総じて、情報が多く透明性が高まるほど生産性が上がる。ウォール街の目的は資本を提供することだ。情報が容易に入手できれば、われわれはより良い仕事ができる。市場は、よりオープンかつ頻繁に報告する企業に報いるだろう」
◎エド・ミルズ氏(レイモンド・ジェームズのワシントン政策アナリスト)
「四半期報告は1934年証券取引法で定められており、議会がこの要件を変更するとは考えにくい。サーベンス・オクスリー法でも開示義務は強化された。また、投資家が投資判断を行う上で重要な事実を、上場企業が開示する義務も存在する。ただし、変更の可能性があるのは四半期ごとの報告内容で、この部分についてはSECに裁量がある」
◎マット・メイリー氏(ミラー・タバクのチーフマーケットストラテジスト)
「透明性の欠如は投資家にとって困難を伴うが、企業経営陣が長期的視点で事業に集中する余地も生む。つまり明らかにもろ刃の剣だ。ウォール街の正確な分析がより重視されるようになる。また、企業が決算を発表する際に多額の収益を得るオプショントレーダーにとってはマイナス要因となるだろう」
原題:Wall Street Raises Alarm on Trump Push to End Quarterly Earnings(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.