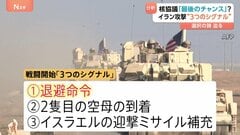・未婚化や晩婚化、核家族化、高齢化の進行で配偶者と死別した高齢単身世帯の増加を背景に、単身世帯の存在感が増している。
単身世帯は1990年では総世帯の23.1%だったが、2020年には38.0%となり、2050年には44.3%となる見通しだ。
その内訳は、かつては若年男性が多かったが、現在は60歳以上の女性(26.1%)や35~59歳の男性(20.5%)が多く、2040年には60歳以上の男女が半数を超える(50.1%)。
・家計消費における単身世帯の存在感も増している。
現在は家計消費全体3割弱だが、2040年には3割を上回るようになる。
60歳以上の高年齢世帯の存在感も増しており、二人以上世帯と単身世帯を合わせた家計消費に占める割合は、現在では4割弱だが、2050年には約半数となる。
なお、高年齢の単身世帯に限ると、2020年頃までは1割を下回るが、2050年には15%程度となる。
・GDP統計の国内家計最終消費支出を世帯構造別に分解し将来推計を行うと、世帯当たりの消費額が少ない高年齢世帯や単身世帯が増える一方、消費額が多い40~50歳代などの家族世帯が減るため、国内家計最終消費支出は2030年頃をピークに減少し、2050年にはピーク時より約15%減少する。
なお、単身世帯では2030年頃、60歳以上の高年齢世帯、高年齢の単身世帯では2045年頃まで増加傾向が続く見通しである。
・日本の消費市場の縮小に歯止めをかけるには、可処分所得は一時期より増えているものの、消費支出が減少している現状を踏まえるとともに、今後とも増加が見込まれる単身世帯の実態を丁寧に捉え、単身世帯特有のニーズに対応した商品・サービスを拡充することが有効だ。
かつては、単身世帯と言えば若年層のひとり暮らしというイメージが一般的だったが、今後は高齢者が増えていくため、単身世帯共通の消費志向に加えて、性年代などの属性による違いに留意した商品・サービスを提供することが重要だ。