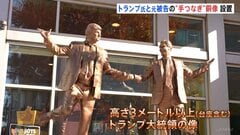(ブルームバーグ):第一生命ホールディングスの菊田徹也社長は足元の国内超長期金利について、需給の緩みによって「オーバーシュートしている」と述べ、行き過ぎた水準にあるとの認識を示した。日本の経済実態を踏まえれば、年末ごろまでには落ち着くとみている。
23日のインタビューで超長期国債市場について「少し前までは考えられないことが起きている」として「ロングオンリーの投資家が極めて限られた状態になり、短期的な投資家が中心になっている」と指摘。国内潜在成長率は1%以下として「マクロ的に見た本当の実需の落ち着きどころは、おそらくもっと下にある」と述べた。
超長期国債の利回りは4月以降、急上昇(価格は下落)している。新発40年国債は今月22日に3.675%と過去最高を更新した。生保など超長期債を保有する投資家は、金利急騰によって含み損が拡大。機関投資家からは超長期金利の安定に向け、日本銀行による買い入れ減額への対応を求める声が出るなど市場の関心は高まっている。
一方、27日の債券市場では超長期債を中心に利回りは低下した。主要投資家である生保グループトップによる「オーバーシュート」発言を受け、市場からは割安修正の買いが見られるとの指摘も出ていた。
第一生命H傘下の第一生命保険が抱える3月末時点の国内債の含み損は2兆400億円と1年前と比べて1兆5000億円超膨らんだ。債券の時価が帳簿価格よりも50%以上下落した場合には減損処理の可能性が生じる。菊田社長は減損について「まだ距離がある」と述べた。
超長期金利の上昇は、主要な買い手である生保の多くで新たな資本規制対応のために積み増してきた積極的な買いが終了段階にあり、買い手が減少している上、財政拡大懸念なども加わり、買いが手控えられていることが要因だ。そのため、菊田社長は超長期国債の需要がなければ発行額が調整されるというケースもあり得るとの見方を示した。

第一生命保険の運用資産(一般勘定)は約33兆8000億円。そのうち日本国債・地方債は16兆6000億円で、その約半分が20年超の残存期間だ。菊田社長は、健全性向上のための資産と負債のデュレーション(平均回収期間)の差を縮める取り組みは終えているとして、超長期債をそれほど買える余力がないのは「事実」とも説明した。
一方、今期(2026年3月期)の国債運用は低利回り債から高利回り債への入れ替えを5000億円程度行う計画。現在の水準は「魅力的」だとした上で積極的に入れ替えを行って、ポートフォリオ全体の収益を上げていくことが「極めて望ましい」と述べた。
アセマネで3000億円規模の投資も
第一生命Hは今月、債券に特化したヘッジファンドの英キャプラ・インベストメント・マネジメントに追加出資し、持ち分法適用会社にする方針を発表した。「債券でものすごく大きなプレーヤー。パフォーマンスもずっと良い」と評価。日本が金利のある世界となる中、「特に金利周りの運用ノウハウをより深く取り込んで理解したい」と狙いを述べた。
現在は株主還元を重視した資本政策を進めている。出資や買収は収益性の高いオルタナティブ領域を中心に行ってきたが、「アセットマネジメント事業ではスケールが足りていない」と言及。将来的には同分野でのさらなるM&A(企業の合併・買収)を視野に入れていることも明らかにした。
30年に非保険事業(新規事業とアセマネ事業)で前期(25年3月期)比約6倍となる600億円規模のグループ修正利益を目指しており、アセマネ事業でのM&Aは「3000億円くらいの投資にはなる」との目線を示した。
(4段落目に27日の超長期債市場の動向を加えて記事を更新します)
--取材協力:Masaki Kondo、間一生.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.