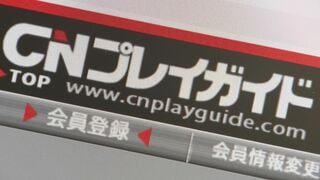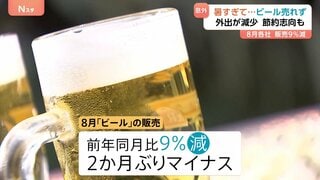(ブルームバーグ):日本銀行の野口旭審議委員は22日、足元の超長期金利の上昇は異常な動きではないとし、日銀が何らかの対応に動くような状況ではないとの見解を示した。宮崎県金融経済懇談会で講演後に行った記者会見で語った。
野口氏は、超長期金利の上昇は急激だが、異常な動きと決めつけることはできないとし、日銀が「むやみに介入、操作するというのは適切ではない」と述べた。金利は将来の予想や思惑を反映してもともとボラタイルに動くものであり、期間の長い金利は米国の政策の不安定性や財政状況を反映した米金利の上昇に連動している面もあるとの見方を示した。
日銀は6月の金融政策決定会合で、来年3月までの国債買い入れの減額計画の中間評価と同4月以降の計画を議論する。機関投資家などから、超長期金利の安定に日銀の買い入れ増額などを求める声が出ていたが、野口氏は自由な金利形成を促す観点から、現時点で静観する考えを示した。

22日の債券相場は下落。超長期債の需給悪化への警戒感や野口委員の発言を受け売りが優勢となり、利回り曲線のスティープ(傾斜)化が進んだ。新発40年国債利回りは一時前日比6ベーシスポイント(bp)高い3.675%に上昇し、3営業日連続で過去最高を更新した。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤原和也債券ストラテジストは、野口氏の発言について「日銀は金利上昇に対してサポートしてくれると期待していたものをはがす内容」と指摘。これを受けて超長期債が売られたと説明した。
野口氏は2026年4月以降の国債買い入れに関して、超長期金利が上昇していることが「直接的にリンクするとは考えていない」と述べた。現行計画では毎四半期に4000億円ずつ減額しているが、新たな計画でペースをどうするかは今後の検討としつつ、「これまでの計画を大きく変えることは恐らくないと思う」と語った。
午前の講演では、来年4月以降の国債買い入れ方針は「より長期的な視点から検討する必要がある」と指摘。バランスシートの縮小は十分な時間をかけて進めていくことが、市場安定に望ましいと述べた。
物価の基調
金融政策運営については、政策金利の調整は「ほふく前進的なアプローチが重要」と強調。「政策金利を1段階引き上げるごとに相応の時間をかけてその経済への影響を確認し、さらにその時々の上下リスクを十分に点検した後に次の利上げを決める」といったやり方と説明した。基調的物価上昇率が2%近傍で安定しつつあることを慎重に見極めつつ、政策金利を調整していくと述べた。
トランプ関税を受けた内外経済の減速懸念の強まりを踏まえ、日銀は1日の金融政策決定会合で政策維持を決めた。その後の米中関税協議の合意などによって過度な警戒感は後退しつつあるが、米関税政策を巡る不確実性は解消されていない。野口委員は利上げ路線を継続しつつ、海外リスクも踏まえて経済・物価情勢を慎重に点検していく重要性を指摘した。
物価の基調はまだ目標地点に到達していないとしつつ、「さまざまな指標はそこに着実に近づいていることを示唆している」と指摘。基調判断では、賃金を反映するサービス価格の動向が重要だとし、その上昇率が2%を上回ることが「2%の物価上昇が持続的・安定的に実現されるための重要な要件」との認識を示した。
ハト派として知られる野口委員は、日銀が昨年3月に決めたイールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)とマイナス金利政策の同時撤廃、7月の0.25%への利上げに反対票を投じた。今年1月の0.5%への利上げには賛成した。
(記者会見での発言や市場関係者のコメントなどを追加して更新しました)
--取材協力:山中英典.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.