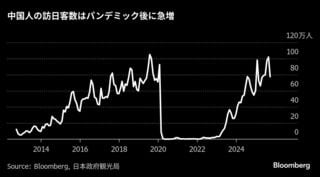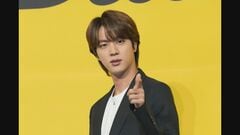(ブルームバーグ):アジアで一部の中央銀行が、経済理論の痛みを伴う再学習を強いられている。
中国やインドなどの通貨当局は、自国通貨の防衛で外貨準備と不透明なデリバティブ(金融派生商品)取引を組み合わせ、長期にわたりドル高対策を続けてきた。しかし、その動きは景気低迷で流動性が必要とされるタイミングで、銀行の借り入れコストを押し上げる結果となった。
中国の翌日・7日物レポ金利は2月に大きく上昇し、利回り急伸が債券投資家に損失をもたらした。インドでは今年に入り、少なくともここ14年間で銀行の流動性が最も深刻な不足に陥り、翌日物の借り入れコストが急速に膨らんだ。インドネシアとマレーシアでは、中銀の為替介入により流動性が枯渇した。
これらの動きは、エコノミストらが「国際金融のトリレンマ」と呼ぶ状況を示している。つまり、国家が通貨を管理し、独自に金利を設定し、資本の自由な越境移動を許容するという3つを同時に実現することはできないということだ。いずれにしても、何かが崩れるか、譲歩を迫られることになるだろう。

ロベコのアジア担当ソブリンストラテジスト、フィリップ・マクニコラス氏は「国際金融のトリレンマの下では中銀が通貨の安定を維持し、資本勘定制度が変わらないと仮定すると、金利が調整メカニズムとならざるを得ない。最初に銀行間市場金利でそれが表面化する」と指摘した。
銀行間金利の上昇は手元資金が不足している兆候で、より広範な経済に打撃を与える可能性がある。銀行の貸し渋りは経済成長を阻害しかねない。
国際金融のトリレンマは、新興国市場の投資家が直面する込み入った問題を浮き彫りにしている。
現地通貨安は、外国人投資家が新興国で保有する株式や債券の価値を直撃するが、一方で為替相場の安定が経済成長の犠牲を伴うものであれば、投資全体が損なわれかねない。
もぐらたたき
自国通貨の防衛がもたらした副作用に抵抗し始めている中銀もある。インド準備銀行は5日、31日の年度末までに債券購入とスワップオークションを組み合わせて215億ドル(約3兆1600億円)を金融システムに注入すると発表。資金不足を打ち消す新たな試みだ。
中国人民銀行は本土内でのデフレ圧力という逆風に見舞われているにもかかわらず、人民元相場に焦点を絞り、これまでのところ大規模な流動性供給には踏み切っていない。
政府が北京で5日に開幕した全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で5%前後の経済成長率目標を発表し、金融緩和が必要となる野心的な目標を掲げたことで、潮目が変わりつつあるのではないかという期待もあったが、7日に国債利回りは再び大きく上昇した。
トレーダーらはトランプ米大統領の世界貿易への大胆なアプローチによって特徴付けられるだろう1年の不確実性に備えている。
アジアの中銀はある日は自国通貨を守り、次の日は流動性逼迫(ひっぱく)を緩和するという「もぐらたたき」のような行動を強いられることになるかもしれない。
インドネシア中銀は自国通貨防衛で新しいアプローチを採用。資本流入を促す狙いで、新しいタイプのルピア建て証券を2023年9月に導入した。
しかし、この証券は銀行システムから資金を引き離し、流動性引き締めの一因となっている可能性があるとゴールドマン・サックスのリナ・ジオ、ダニー・スワナプルティ両氏らストラテジストは2月26日のリポートで指摘した。
マレーシア中銀は通貨先物を活用してリンギットを支えているが、ロベコのマクニコラス氏によると、これは預貸率の高さと相まって、銀行間での流動性を逼迫させている。
ドル高に抵抗する中銀が、痛みを味わっているのは皮肉なことだ。
トランプ大統領が大統領経済諮問委員会(CEA)委員長に指名したスティーブン・ミラン氏は、ドル高が米国にもたらすコストについて広く論じており、トレーダーらは最近、ドル安の長期化につながる可能性のある「マールアラーゴ合意」の可能性を注視している。
アジアの中銀にとっては、ドル高のコストに直面せざるを得ない状況が一段と深刻化しているため、そうした合意はそう悪い考えではないかもしれない。
原題:‘Impossible Trinity’ Conundrum Has Caused a Cash Crunch in Asia(抜粋)
--取材協力:Wenjin Lv.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.