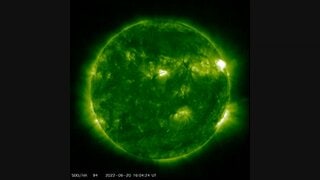(ブルームバーグ):セブン-イレブンは長年、「近くて便利」だと消費者にアピールしてきた。確かにそうだ。コンビニエンスストアでの買い物は少し割高だが、便利さはそれを補って余りある。しかしこの頃、親会社のセブン&アイ・ホールディングスは多くの時間を無駄にしているように感じられる。
カナダのアリマンタシォン・クシュタールからの買収提案を拒み続けているセブン&アイは数カ月にわたり、コンビニ事業で競い合うファミリーマートを傘下に持つ伊藤忠商事という異例のパートナーを巻き込み、経営陣による自社買収を通じ経営権を日本側にとどめておこうと試みてきたが、結局は失敗に終わった。
そして最近、買収を阻止する次の策として、セブン&アイの井阪隆一社長が退任し、社外取締役である米国人のスティーブン・デイカス氏が後任に就くと日本経済新聞が報じた。
この動きは、不採算の国内スーパーマーケットチェーンや、同社のディスカウント戦略に貢献してきたコンビニ以外の事業を排除し、同社のグローバル展開に新たな顔ぶれで臨むことを目的としているようだ。
セブン&アイには新しいイメージが必要なのかもしれない。10年前にアクティビスト(物言う株主)に注目されるようになって以来、同社は市場とのコミュニケーションに苦労してきた。株価の低迷は、海外展開による売上高の急増を継続的な利益増加につなげられるのかという懐疑的な見方を反映している。
だが、小売業界の動きは速い。クシュタールの攻勢に対する防衛に時間を費やしている間、経営陣が戦略的な機会などへの対応に時間を割くことができない。
井阪氏は2016年に社長に就任。米投資ファンド、サード・ポイントのダニエル・ローブ氏が、それまで同社を率いていた鈴木敏文氏による世襲の動きに警告を発したことが井阪氏の社長昇格を後押しした。
競争が激化する中でセブン-イレブンの日本事業を築き上げてきた井阪氏をローブ氏は評価した。クシュタールの買収提案により、セブン&アイが今、コンビニ分野で最高水準の地位を築くのに貢献した井阪氏を排除せざるを得なくなったことは、懸念すべきことだ。
セブン&アイは、クシュタールの攻勢をかわすため、複雑な方法を検討し続けている。経営陣による買収案に加え、クシュタールに逆買収を仕掛ける「パックマン・ディフェンス」という選択肢を一時的に昨年検討していたという報道も浮上した。
最終的に、セブン&アイはそれはあまりにも難しいとの結論に至ったようだが、皮肉なことに、その理由の一部は、カナダの買収規定の運用が外国人投資家にとって非常に難しいということだった。
コンビニの魅力
クシュタールのセブン&アイ買収計画が伝えられた当初から、ビジネス誌の焦点はこの取引の画期的な特性と今後の日本企業絡みのM&A(企業の合併・買収)にどのような影響を与えるかということに置かれていた。
M&Aを扱う弁護士らは日本にはこれまで過小評価されてきた資産が山ほどあり、こうした企業や資産が外国勢によるM&Aの俎上(そじょう)に載りそうだとの見通しに期待を膨らませている。
しかし、クシュタールの買収計画自体がもたらすものについては、あまり注目されていない。恐らくそれはコンビニで売られているサンドイッチの具のように薄っぺらなものだからだろう。
セブン&アイができないのに、クシュタールが日本のコンビニの魅力を米国の店舗にもたらすことができるとは、私には思えない(地理的要因による物理的な課題が、この買収実現の障害になりそうだ)。
数カ月にわたる交渉の後、この両社の統合が日本や米国、あるいは両国の独占禁止法当局によって阻止されないとすれば、最も可能性が高いと思われる結末は高い買値により、新会社が負債に苦しむことだ。
そもそも、何のための買収提案なのか。うらやましいほどの利益率を誇るクシュタールだが、顧客やサプライヤー、フランチャイズオーナーを含む利害関係者にとって、日本の企業よりも優れた経営ができるという証拠があるだろうか。
セブン&アイがコンビニ中心の事業に転換することは、投資家が10年近く前に要求し始めたことだが、まだ緒に就いたばかりだ。論理的な結論を導くため経営陣にはより多くの時間を与えるべきだ。株主にとっての一時的な利益以外に、今回の取引のメリットは見当たらない。
急速に変化する時代において、ビジネスに何のプラスにもならない取り組みに貴重な時間を費やしていることになる。クシュタールはすでに敵対的な買収はしないと表明している。
そのため、セブン&アイは水面下でさまざまな代替案を練るのではなく、クシュタールに対し丁重かつ毅然(きぜん)とした態度で、別の形で事業を変えていくと伝えるべきだ。結局のところ、それがコンビニの素晴らしいところだ。別の選択肢はいつもすぐ近くにある。
関連コラム:
- 【コラム】セブン&アイと伊藤忠、M&A巡る意外な連帯-リーディー
- 【コラム】7-イレブンの価値、株主至上主義で測れず-リーディー
- 【コラム】7&i買収提案、海外勢が日本の大企業に触手-リーディー
- 【コラム】7&i再編に説得力なし、独禁法も買い手に有利-ヒューズ
(リーディー・ガロウド氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、日本と韓国、北朝鮮を担当しています。以前は北アジアのブレーキングニュースチームを率い、東京支局の副支局長でした。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:7-Eleven’s Time-Wasting Isn’t So Convenient: Gearoid Reidy(抜粋)
コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:東京 リーディー・ガロウド greidy1@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Patrick McDowell pmcdowell10@bloomberg.net
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.