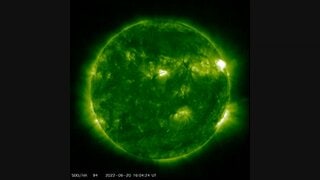(ブルームバーグ):日本企業の合併・買収(M&A)案件増加が、アナリスト調査の少ない中小企業に投資するファンドに高パフォーマンスをもたらしている。
ニッチ・ジャングル日本株オーファン・カンパニー・SDGファンドはブルームバーグのデータによると年初来6%以上のリターン(2月末まで)だ。ユーロベースのTOPIXスモール指数(税引き後配当込み)の3%を上回り、同様のファンドで上位1%に入る。これまで利益を得た20社のうち半数は2022年のファンドに立ち上げ後に買収された企業だ。
日本企業へのガバナンス(統治)や株主還元の圧力が強まり、ブルームバーグのデータによると買収につながりやすい株式公開買い付け(TOB)案件数は昨年94件とさかのぼることが可能な1998年以降で最多、今年も2月25日時点で24件と初めて年100件を超すペースで増えている。こうしたM&A案件がファンドのパフォーマンスを押し上げている。
運用会社ニッチ・アセット・マネジメントのファンドマネジャー、マッシモ・バジアーニ氏とアンドレア・アンドレアス氏はブルームバーグのインタビューで投資基準について、アナリストの調査が皆無またはほとんどない日本の小型株でネットキャッシュを持つ割安株だと明らかにした。
ファンド運営については、ポートフォリオに含まれる約150社のうち7割以上の企業に取材している株式アナリストのサリーナ・レッグ氏の調査を基にしている。 対象企業は少なくとも10年間の上場、最低でも約20億円の浮動株があることを条件にしている。
株価3倍も
ファンドでポートフォリオ比率が最大(2月14日時点)の中央紙器工業は、ニッコンホールディングスによる1月末のTOB発表を受けて株価は3.7倍以上に上昇した。また投資していたフェイスは昨年11月からのGenesis1によるTOBを受けて株価は3倍以上になった。フェイス株は1月30日に上場廃止になっている。

こうした中小企業への投資は株価大幅高が期待できると同時に、市場での取引量が少ないという流動性リスクを抱えている。投資している遠藤製作所はブルームバーグのデータによると、過去1年間で1日平均2万2000株程度の取引なのに対してトヨタ自動車は2900万株以上ある。
こういった流動性リスクを軽減するためにファンドは保有株の一定割合を迅速に売却できるようにしている。また現金はポートフォリオの5-12%を占め、その半分はユーロに対してヘッジされている。
バジアーニとアンドレアス両氏は日本株ファンド以外にも2022年に韓国でもファンドを設立、23年にはインドネシアの小型株のファンドを始めている。
日本の中小企業は国内販売に依存しており円高の影響を受けにくい側面がある。このため中小型株への投資は、米トランプ政権誕生を契機とした世界的な貿易戦争や日本銀行の政策金利引き上げによる円相場の乱高下からの避難場所になり得る。
保有企業の多くが幅広い市場でほったらかしにされているとバジアーニ氏は指摘、「ポートフォリオに含まれる企業はすべて買収の対象となり得る」、「日本の中小企業の質は素晴らしい」と述べた。
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.