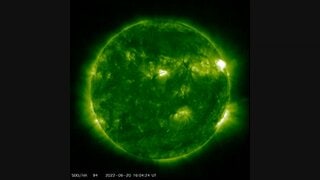(ブルームバーグ):こんにちは。布施太郎です。今月のニュースレターをお送りします。
親子上場は、日本独特の資本政策だと言われてきました。親会社が議決権の50%以上を保有し、支配権を持ったまま子会社を上場させる形態です。親会社と、子会社の少数株主の利益が必ずしも一致しないケースがあり、常に両者の利益相反が懸念されています。
東京証券取引所は親子上場そのものを認めた上で、親会社と子会社の双方に情報開示の充実や、子会社での独立社外取締役の確保などを通じて少数株主の権利が損なわれないようにすることを求めています。昨年始まった新しい少額投資非課税制度(NISA)は活況を呈しています。個人が株式市場に参入する時代において、少数株主の利益を確保する企業の取り組みは十分になされているでしょうか。
今回は、日本製鉄の子会社を巡るアクティビストの動きを通して、その問題を考えてみました。
流通株式比率に照準
日本製鉄とアクティビストが、子会社を巡って攻防を続けている。米国ではUSスチール買収の先行きが見通せない日鉄だが、国内では株式市場との向き合い方で隙を突かれた格好だ。日本独特の親子上場のあり方が問われている。

攻防の舞台は、システム開発の日鉄ソリューションズ(NSSOL)と鉄鋼業の大阪製鉄。いずれも日鉄が発行済み株式の60%以上を握り、東証に上場している。
NSSOLの株式は、シンガポールの3Dインベストメント・パートナーズが9.4%を、大阪製鉄はストラテジックキャピタルが15.3%を保有している。
アクティビストの狙い目は「流通株式比率」だ。東証の上場維持基準の一つで、所有が固定的で流通性が乏しい株式を除いた株式の比率を指す。一般投資家の売買がスムーズに行われるようにしたり、価格形成の公平性を確保したりするためで、プライム市場では35%以上、スタンダード市場では25%以上の流通株式が必要とされる。親会社とは別の投資家が買い進めて流通株式比率が基準割れになると、上場廃止に追い込まれる可能性が高まる。
日鉄の対抗策
プライム上場のNSSOLは昨年8月以降、3Dが買い増しを進め、11月には保有比率が8.35%にまで上昇した。日鉄と3Dの持ち分を合わせると70%を超えてしまう。3Dが10%以上保有すると固定株と見なされて流通株式とはカウントされなくなってしまうため、NSSOLはプライムでの上場が維持できなくなる可能性が現実味を帯びた。
NSSOLが打ち出した打開策は、上場維持基準が東証よりも緩い名古屋証券取引所メイン市場と福岡証券取引所本則市場への重複上場。それぞれ1月に上場した。
両市場の流通株式比率の上場審査基準は25%以上だが、上場維持基準は名証メイン市場が10%以上で福証本則市場は5%以上。プライム市場やスタンダード市場で上場が維持できなくなっても、名証と福証では上場し続けることが可能となる。NSSOLは両市場への上場の目的について、「個人株主の増加を図るとともに株式の流動性を確保すること」と説明している。
スタンダード市場に上場している大阪製鉄も、ストラテジックが買い進め、昨年10月時点で9.5%を保有。日鉄の60.6%と大阪製鉄の自己株式7.9%を合わせると、流通株式比率が25%を切る水準に直面した。
そこで日鉄が取った対抗策は、自らの保有比率の引き下げだ。大阪製鉄は1月31日、TOB(株式公開買い付け)価格が足元の株価を下回るディスカウントTOBを実施すると発表し、日鉄はこのTOBに応募すると公表。最終的に大阪製鉄が実施する自己株償却により保有比率を55.6%に減らし、ストラテジックの持ち分14.1%(自己株償却後)と合わせても流通株式比率が25%を割り込まない水準に維持するのが狙いだ。
大阪製鉄はTOBと同時に福証本則市場への上場申請も発表。将来的に25%を下回っても上場を継続させる算段だ。
ただ、ストラテジックは2月に入ってさらに大阪製鉄株を15%超にまで買い増しした。TOBと自己株償却を行ってもストラテジックの保有比率は20%程度になる計算になる。このため、ストラテジックは大阪製鉄が流通株式比率基準に抵触するのは確実だとし、TOBの取り止めと日鉄のTOBへの応募撤回を求めた。
少数株主との利益相反
「大阪製鉄は貴社(日鉄)とは利益の方向性が必ずしも一致しない少数株主が存在しており、長年にわたり利益相反が発生している」。ストラテジックは、昨年11月に公開した日鉄宛ての書簡でこう指摘し、日鉄が大阪製鉄の全株式を買い取って完全子会社化するよう要求した。
大阪製鉄が上場を継続する場合には、自己資本利益率(ROE)向上実現に向けた具体的な計画の策定と実行、さらに少数株主の利益を保護するガバナンス体制の構築や日鉄による保有比率の引き下げなどを要望した。
親子上場は常に、親会社と子会社の少数株主との間の利益相反のリスクをはらむ。みずほ証券の菊地正俊チーフ株式ストラテジストは「欧米では少数株主保護の考えが厳しく、ないがしろにした経営をすると株主から訴えられて負ける可能性が高い」と指摘。「日本は少数株主保護に対する意識が低い」として日本の現状は世界的に見ると異例と話す。
東証は2月4日、親会社と子会社双方に「グループ経営や少数株主保護の両面から、親子上場のあり方を取締役会で継続的に検討し、開示や投資家との対話を通じて適切に説明責任を果たすことが求められる」とする文書を公表した。「親子上場の意義について、投資者の目線を踏まえた検討が行われていない」などの指摘が寄せられていると説明している。
日鉄はコーポレートガバナンス報告書で、子会社の独立性を確保するために独立社外取締役が3分の1以上を占める体制にするなどと記載しているものの、子会社をあえて上場させている意義には踏み込んでいない。子会社2社もそれぞれの報告書で、なぜ親会社の傘下での上場が必要なのかを説明していない。
日鉄と子会社2社にコメントを求めたが、日鉄の広報担当者は、現時点で答えられることはないとコメント。大阪製鉄の担当者は回答を控えた。NSSOLの広報担当者は「自律的な経営を進めることで日鉄グループ外からの情報も増加。日鉄にとってもグループ外から得た知見がグループ内に展開され競争力強化につながる」と回答し、互いに親子上場によるメリットを享受できるとした。
大和総研の神尾篤史主任研究員は一般論として「投資家としては、子会社がもうかっているのであればなぜ100%取り込まないのか、もうかっていないのであれば中途半端に保有している理由を説明してほしい」と語る。
親子上場そのものは、日立製作所がすでに全廃、富士通なども削減に大きくかじを切るなど減り続けている。東証によると、上場子会社数は2014年の324社から24年には230社に減少した。一方で、大株主が株式の20-50%未満を握る上場会社数は14年の741社から987社に増加。大株主と少数株主の間の利益相反が懸念される会社は増えている状況だ。
資産運用立国を掲げて国民に証券市場への参加を広く呼びかける以上、少数株主の利益や権利の確保は必要不可欠だが、その道はまだ途上のままだ。
(NSSOLのコメントを追加し更新します)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.